
|
北山最後の秘境であわやの谷遡行
滝谷〜天狗峠(P928)〜 フカンド山(P852三等三角点)〜久多峠 |

|
| 馬尾の滝 |

|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009.6.27(日)晴れ Oさん 小てつさん Ikomochi
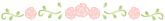
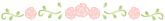
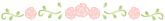
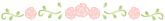
先日UPしたあわわの比良大岩谷に続き、今回も命拾い体験記(大汗)です。小てつさんから「Oさんが三国から天狗峠に行こうと言っているけど・・」とメール、もちろん即「行きます」と返事。 ところで、コースはどこを行くのか?と尋ねてもいまいちはっきりしない。その日に決めるというのだ。で、ネットや本で三国岳や天狗峠あたりの記録を探し、地図を広げる。天狗峠直下に滝谷という急峻な谷があるそうだけど、まさかそこは歩かないよね。でもまあ念のために調べておこう。
さて、当日、稲妻号と流星号で久多峠を目指す。Oさん「ここに1台置いときましょ」えっつ もしかして三国から尾根をロングで来るわけ???久多の集落から林道をひた走り、岩屋谷分岐を越え「ここがいいなあ」と停めたのは滝谷の入り口である。ひえええええ 最悪コースに行くんや 行ってみたいのはやまやまだけど、大丈夫やろうか?不安がよぎる。 川を渡ると杉木立の山道を進む。30分も行くと、滝音がして立派な滝が目の前に現れた。一の滝で落差30mの連瀑。マイナスイオンを全身に浴びご機嫌だ。また谷の上部を巻いていくと、足元に見事な滝を見下ろす。馬のしっぽのようなので馬尾の滝という落差15m滝。滝の上部は苔むした沢が続き、楢の大木が緑濃く、すばらしい谷だ。
Oさんの先導で渡渉を繰り返しながら、どんどん高度を上げていく。滝谷入り口から1時間で、谷分岐に到着。ここで3つに谷は分かれ、二の谷、三の谷は岩場と大滝が続くという。ところで、この週は忙しくて毎日が不規則な上 食欲もあまりなくて、パンや麺類で過ごすことが多かった。この朝も食欲がないからパンとバナナなどを食べてはきたのだが、谷に入ってから蒸し暑いのと合わせてなんだか身体の中から力が湧いてこない。分岐でゆっくり休憩し、パンをかじったり飲み物を摂りなんとかエネルギーをつけようとがんばった。
Oさんは、沢登りと岩登りをするといって二の谷にむかって斜面を登っていった。大きな滝があるのだそうだ。ひょいひょいと軽い身のこなしで、山中に消えた。 わたしたちは比較的緩やかな一の谷に挑戦することにして、明るい谷間を進む。流れに沿って踏み跡がはっきりあるのでどんどん進む。30分も行くと次第に谷は急な岩場の連続になり、頭上には木々が生えた急斜面が広がる。ネットの記録でみた谷の風景をみつけ、ここを右手にとって行こうか 本谷らしきほうへと進む。しばらく先の分岐は倒木でふさがれ その先が分からない。ここは確か左のはずやった。で、細い流れをよじ登っていく。斜面にはさまれた流れは岩場の連続。登山靴では足元がすべりそうで、沢靴持ってきたらよかったなあ と悔やむ。
沢の横の傾斜にとりついて腕力でよじ登ることだろうか それともこのまま沢伝いに登ることだろうかと 小てつさんとコース取りを悩みながらも切り立った岩場を登っていく。先導する小てつさんがひときわ大きな背丈ほどの岩をよじ登り、「こっちに足をかけたらいけますよ」と手を差し伸べてくれた。上を覗くと、この岩を越すと沢は緩やかに稜線に向かっているようだ。だが 表面が滑らかな岩ではどうにも足場が悪いのでどこに足をかけるか探したり、足元の沢に落花した黄色い花を愛でたりして、身体を持ち上げるエネルギーをため・・・。
しばらく逡巡したが思い切って岩に足をかけた。底がフェルトの沢靴なら岩の浅いでっぱりにも滑る岩にも足場を確保できたのだろうが、いかんせん分厚い山靴の底では引っ掛かりが少なく持ち上げた足は岩の上まで届かず、あっという間にバランスを崩し片足がずるりと滑り、身体もずるりと落ちた。頭上で「はっ」と声にならない叫びが聞こえ、一瞬に緊張感であたりは満ちる。小てつさんの顔が青ざめるのが、凍った空気を通じて伝わってくる。「やばい このまま滑り落ちたら、谷底に転落してしまう!」 背中の後ろには空しかなく 周りに掴まえるものはない。とっさに靴先を平らな岩にひっかけ足元を止めた。幸いに指は岩の窪みをしっかり掴まえていた。
もう一度同じ岩場を登るのは怖いので、右手斜面の木立に取り付いてよじ登ることにした。こちらも、一歩間違えば、谷底へ転がり落ちる。小てつさんが斜面を横切りロープを木の幹にかけてくれたので、伝って大木の幹にしがみついた。頭上の稜線を目指し、ロープの助けを借り、木の幹をつかみ急斜面を夢中で這い登った。すぐに斜面は緩やかになり先ほどの沢の源頭部、さらに見下ろすと右側に緩やかな勾配で沢が上ってきている。もう少し我慢して上流に進んでから、稜線に上る筋を目指せばよかったのかも。けど、この谷筋はどこがどうなっているのか 緩やかでもなにか障害がありそうで、行ってみないと信用ならん。 10分ほどで、1mばかりの幅のユリ道に出会った。やっとたどりついたみたい。あーしんど。小てつさん「あの時はもうあかんと思ったわ。」わたしはもうへとへとで、昼ごはんまで待てないからと おにぎりをほうばった。ポカリも飲んだ。けれど、消耗したエネルギーは大で、体力はなかなか回復しない。飢餓感が増すばかりだ。20分ほどユリ道に座りこんでいただろうか。
こうもしていられない。お御輿をあげ、ユリ道を天狗峠方向目指す。すごいなあ こんな山道があったということは 昔から人が行き来していたんやなあ とユリ道発見を喜びながら北に少し進むと、稜線に出て、三国岳方向との分岐点に出た。 巨木が立ち並ぶ尾根に登ると、小ピークに1本のこぶだらけの巨大な杉の木。天狗峠分岐だ。この木に、Oさんがちょっと変わった目印をつけたというので見る。木の下の広場で、本格的昼食にした。小てつさんが沸かしてくれた熱い味噌汁がお腹にしみた。飢餓感が満たされ、さっきの恐怖心がどこかに飛んでいった。が、「ほんま もうだめかと思いましたよ」と小てつさん しみじみ言う。上からずり落ちるところを逐一見ていた小てつさんは、どうすることも出来ず生きた心地しなかったやろうな。あー肝が冷えました。やれやれ。
ほっこりしていると、山頂方向から人の話し声がして、菅笠をかぶった一団がやってきた。「あれ 先週 峰床山でお会いしませんでしたっけ?」滋賀のその方たちと、しばしおしゃべり。府立大小屋へ下るという方たちと別れた。 二の谷を登ったOさんとピーク921で落ち合う約束だが、時間は大幅に遅れている。急いで山頂にむかう。巨大なブナが立ち並ぶ道を辿ると、あっけなく広場に出て、そこが北山最後の秘境といわれる天狗峠であった。見晴らしはなく、どうっていうこともない山頂であった。連なる山並みでも見えたら、来たぞ!と感慨一入やったかも。すぐに引き返す。七瀬への降り口を探したが、よくわからなかった。
天狗峠から稜線伝いに尾根道を進む。P921に40分ほどで着いたが、Oさんの姿はない。小刻みにアップダウンを繰り返し尾根を進む。おーい おーいと叫びながら歩き、P927手前で待ちくたびれているOさんとやっと合流した。もう15時を回っていた。
昼食を取り元気が回復したのもつかの間、暑い尾根歩きで水分が蒸発して喉がからから。身体が重い。ここで、小てつさんに山の茶店を開店してもらう。抹茶2服も所望。甘い和菓子とビタミン・カフェインたっぷりの抹茶で、体内の干からびた細胞が活性化していくのが分かる。 P927では、小野村割岳から佐々里峠へと続く尾根道の分岐を見る。はっきりとした山道が下っていた。さあて これから先はまだまだロングトレイル。Oさんの先導で不鮮明な道を下り、細長く延びる尾根に乗る。尾根には点々と黒焦げの大木が立ち並ぶ。落雷によるこげだそうだ。よほどここらは雷の通り道とみえる。数え切れないほどの黒こげ杉を見て歩くことになる。 北東に見える長い稜線。「あのあたりが丹波越えの峠やで」稜線の窪みを指差すOさん。あれが丹波越えかあ 行ってみたい峠であるなあ。小てつさん 行こうな。(連れて行けよ!)しかし、さらに山深そうなところやなあ。
広く平らなP897。昔、板取り(ばんとり)したという大杉のある広場を過ぎる。左手にきゅっと折れて細い尾根に乗る。次のピークで古い芦生杉を通り過ぎ、Oさんが「さあ どっちに行くかな?」と謎かけ。踏み跡は右側の稜線に続いているのだが・・・。やおらOさんは左側の笹の斜面を下りだした。ここは迷うポイントという。フカンド谷への道が合流しているとか。あわててOさんの後を追い、斜面を下ると細い尾根道に乗った。最後の力を振り絞り18:00フカンド山到着。あー もちっとや。しかし、疲れた。
フカンド山からすぐに尾根の分岐。久多中の町に下る長い尾根と、久多峠に下る道が分かれる。薄暗くなった山道をどんどん下ると、やっとやっと見慣れた久多峠の車道に出た。時計は19時をまわっていました。このあたりなぜか携帯が繋がる。久多に鉄塔があるそうだ。帰宅が遅くなると、家人にメールしておく。 デポしたもう一台の車を滝谷入り口に回収しに行き、梅ノ木からひたすら京都を目指し走った。久多の三叉路で飲んだ、冷たいポカリのおいしかったこと。生き返るとはこのことか。今日はなんども生き返ったっけ。 長く厳しいコースであった。まさかあの滝谷に行く羽目になろうとは。しかし、まさかの天狗峠の道をたどれたのは、こんなチャンスであったればこそ。
「北山2」地図のコースタイムは 天狗峠へ12時間。いったいどんなところや?と興味津々であったが、12時間とはネマガリタケが密生していたころのこと。(昭和61年の記録では藪こぎで苦労している)。今はわずかに名残の笹薮があるものの、見通しのよい尾根が続く。 帰宅して家人に、自分の体力以上の山に行くなとさんざん怒られた。そう 今回は準備不足の体力であった。わたしのせいで みなさんの足をひっぱり時間がかかった。しゃりばて の怖さ、今までも数回経験したけれど今回は切実だった。あわやの滑落未遂も一重にエネルギー不足とコース取りのミスである。(帰ってから地形図を確かめると、等高線が込み合った一番きついところを登ったようだ)
以後、山行の前日はしっかりと米を食べ、出かける朝も米粒を口にするようになった。昼食は豪華おかず付のおにぎり弁当を持参し、味噌汁とともにゆっくりと栄養を補給することが常となった。また、エネルギー不足になりそうな時には、時間に関係なく早弁することにしている。山でいったん飢餓感に襲われると、いくら食べても飲んでも「砂地に水」の有様なのがよっく体感できた山行でありました。と、反省多々でありますが、やはりロングコースを歩いた達成感はなにものにも代え難い。(翌日 足指に水ぶくれができ、しばらくけだるかったけれど。)
ずっと気遣いしサポートしてくれた小てつさん(怖い思いをさせてごめんね)、複雑な山域を案内してくれたOさん 感謝です。
* 2010.5.15okaokaさんの記録に滝谷遡行があります。参考にしてください。
【記: Ikomochi】 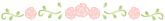
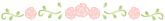
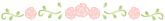
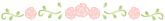
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||