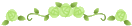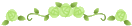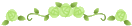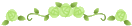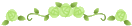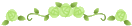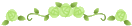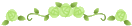|
2010年5月10日(月) 小てつ
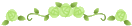
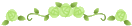
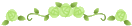
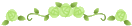
よもやま話など偉そうに書かせていただいている小てつであるが、「比良」
は全くの未経験の若輩者。釣りや嫁の実家に帰省の折に、161号線バイパ
スから見上げる「比良」の角度は尋常ではない。
「あんなとこを登ってるやつは変態や・・・。」
小てつの前々からの、思いである。どちらかと言えば、山頂を極めることを
目的とせず、昔の人がそれこそ炭を担いで歩いたろう古道を探索するほうに
おもしろみを感じているものだから、せっかくジョーさんに、黄スミレの情
報をいただいていても、雰囲気「比良」は後回しになってしまう。そんな折、
「葛川越えに行かへん・・・?」
おなじみの「悪魔の誘い」である。○○越えと名がつけば、それは「ノッコ
シの古道」じゃないか。小てつの「比良後ずさり症」の背中を押すものがあ
る。
話は変わるが、この「悪魔の誘い」を度々してこられる捜査員Iであるが、ま
たまた紀行文が途切れて久しい状況にある。「ふーちゃん」さんも待ち遠しい
ようだ。病気や怪我で山行できなくなっている訳ではなく、ただ単に紀行文
を書いていないだけで、あちこち元気に歩かれているので読者の方々には安
心していただきたい。どうやら、紀行文本文ではなく、踏破した山地図の制
作に難儀しているようで、皆さんには、「そんなんどうでもいいから、先へ進
め。」と、メール攻撃してもらいたいものだ。
さてそんなこんなで、「小てつ比良初踏み」となった訳だが、いつものように
「出町柳」で待ち合わせ、161バイパスから「大谷川林道」を上がって行く。
徒歩でのアプローチなら、ここで歩きが終わってしまいそうなほど「稲妻号」
で林道を走り、登山口近くの大きな砂防ダムあたりにデポし、準備をしてい
る時には快晴だった。見上げる「比良」の稜線は所々に白い岩が露出し、京
都北山の様相とは、やはり一味違った。
また、「クサギ」がはびこる「八丁」あたりに対して、ここは「ヤシャブシ」
が谷を覆いつくしている。「私、これ苦手なの。くしゃみがとまんなくなっち
ゃって・・・。」と言われる喫茶店のおかみさんが見たら、卒倒ものだ。
さていよいよ歩き出せば、見上げる稜線とは裏腹に、山道の勾配はそんなに
キツクない。適度にジグを切り調子よく高度をあげる。なるほど使い込まれ
た道である。それに踏み跡もしっかりしていて京都北山に比べれば、ハイウ
エイだ。
「実はこれが怖いんよ。」
捜査員Iが語る。
「登山道がなまじハイウエイなもんだから、ひとつ道を失くしたら余計にあせ
ってしまうのね。」
なるほどそれは言える。京都北山のとある山域なんて、初めから道が無いん
だからあせることもないし、磁石と地図頼りになるから、しょっちゅう現在
地と見比べることになる。ここじゃ安心しきっていて歩いてるもんだから、
しょっちゅう地図を見るなんてことないだろうし、迷ってから地図を引っ張
り出したところで、現在位置の特定なんてできないだろう。
と、どうしたもんか稜線まであと少しというころになって、雲行きが怪しく、
おまけに急激に冷えてきたようだ。何やらチラチラするものがあるなと思っ
ていたら、いよいよ雪が降り出してきた。入ったばかりとは言え、暦は4月
なんだけど・・・。
一気にまわりはガスっぽくなり、お楽しみにしていた眺望は望めなくなった。
比良はそんなに甘くはなかったのである。
「おとといきやがれ、出直して来い!」
と比良に言われちゃった訳だ。
でも時間は丁度お昼になり、風と雪を避けたところで食事をしようと場所を
見つけた。小てつはこんな時こそ暖かいものをと、バーナーセットに余念が
無い。その時、やっと体勢を整えたと思われた捜査員Iの膝の上から、「土佐
文旦」がポロリと落ちた。
ほんの最初は手を伸ばせばつかめそうな勢いで、ともすれば追っかけようか
と思うやいなや、「土佐文旦」はあっという間にスピードを上げ転がり落ちて
いく、見えなくなる少し前には、樹幹を飛んでいるようだった。
「あ〜ん、せっかくお昼に食べようと、重い目して担いできたのに〜。」
捜査員Iが嘆くが、あとの祭り。それより、その加速度の恐ろしさに小てつは
唖然である。
(ここで転んだら、ただじゃすまんで・・・。)
なんやかんやで結局「烏谷山」の頂上だけ踏み、そそくさと降りにかかる。
それにしても寒くて、歩いていても手指の先が温まらない。お昼に暖かいも
のを食べて、手袋もしているにかかわらず。きっと急激に冷えたせいだろう。
こんなのがもっとキツクなって、動けなくなり、遭難ってことになるんやな。
でも不思議な水場まで降りてくれば、もう余裕である。恒例の「野点タイム」
を楽しむことになり、店を広げる。お茶をたててくつろげば、
「あ〜それにしても悔しいわ、「土佐文旦」。ここらに転がってきてへんやろか。」
あきらめの悪いお方である。
「きっと今頃、鹿のエサになってますわ。あの「土佐文旦」、実はまだすっぱく
て、人間様の口には合わんと、神様が言わはったんですわ。」
「比良」も「土佐文旦」も、甘くはなかったんでしょう
という話
【 記: 小てつ 】

|
| あ〜それにしても悔しいわ、「土佐文旦」
|
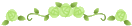
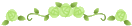
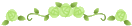
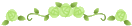
|