
| 愛宕山 中尾根〜岩ヶ谷 |

|
| 神社前 |

|

|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2011年1月30日 (日) 晴れ 小てつ
参考タイム 保津峡7:27着〜中尾根取り付き7:47〜大岩8:33〜水尾8:55〜岩ヶ谷取り付き9:15〜お墓11:20〜ジープ道出会い11:27〜三角点11:44 三角点12:15〜地蔵辻12:27〜神社裏道分岐12:38〜水尾道合流13:17〜水尾13:34〜保津峡14:20 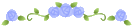
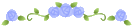
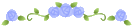
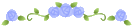
その気になれば自宅から歩いて登れるという、小てつにすれば本当に地元の山「愛宕山」。毎年お正月の初山には愛宕、地蔵、竜の三山めぐりが恒例になっているものの、去年はそのお正月に一回行ったっきりで、(高島で浮気してたせい???)これじゃあまたお会いしたいなと思っているTOSHIさんともお会いできるはずもなく、この週末の冷え込みで北山はどこの山も強敵みたいなので、それではと「愛宕山」に行くことにしました。でもって、とても印象深い山行となりましたので、紀行文にしようかと。 愛宕に行くにしても、この時期、コース取りを考えるのが難しい。最初は「梨の木谷」を「くびなし地蔵」に直登し、「竜の小屋」を突き抜けて芦見谷の林道からE362A009の雑木林の尾根をスノーシューで歩いてみよかとも思ったんだけど、時間がかかりすぎると思うのとエスケープのルートがないことから、それじゃあ新しい靴での「ワカン」での歩き具合を確かめるために、「岩ヶ谷」を歩いてみようと思いました。 この「岩ヶ谷」、結構雪のたまる谷で、雪のジープ道から幾度と突入しかけるんだけど、いつも断念。上からダメなら下から攻めようという訳で、下からならヤバくなったら降りればいいという考えで。 前日、遅くに帰宅の娘が、「外は吹雪いている。」というので、早々に稲妻号での出動を断念していた小てつ、JRで保津峡に行くことにする。駅までのコンビニでおにぎりを仕入れホームへ、ホームから見える愛宕山は全然白くない。娘のいった吹雪はなんやったんやろ? 保津峡駅に降り立ったホームにも、はしっこのほうに寄せられた雪が残る程度で、地面は乾いてる。(なんじゃこれやったら、稲妻号で六丁峠越えられたんちゃうん!)ということだけど、冬の朝は何が起こるかわからないし、無理は禁物。
保津峡駅から「つつじ尾根」ならすぐに山に入れるけれど、最初から崖登りなのがいやなので、ウオーミングアップがわりができる「中尾根」へと向かう。この保津峡付近、嵐山から別れてきた「猿」の群れがいるので気をつけなければいけない。 お正月のコースは、大杉谷〜三角点〜地蔵〜滝谷〜竜〜梨の木なので、他のどのコースも2年ぶりとなる。さて2年ぶりの中尾根の取り付きの、車の離合のために拡幅されたガードレールのところでスパッツをつけストックを延ばす。 取り付きにあった○サのテープやその他の目印は全部無くなっている。しかし、登り始めると(中尾根ってこんなに道がはっきりしてたっけ???)と思うほど、道の分だけ下草がはげて、団体さんが歩いたんかな? 雪は全く無いけれど、霜柱がたち、歩くたびガシガシ気持ちいい。この「中尾根」は適度に勾配がきつくなったり、ゆるくなったりで、結局同じところに出る「つつじ尾根」より楽に感じる。小てつは「つつじ尾根」を、降り専用で利用している。ただ「つつじ尾根」は南に向いているので、この時期午後にはベチャベチャになっていることが多いから、選択には注意が必要だ。 それにしてもテープ類がきれいに掃除されている。しかし、これが本来の山。ちらちらテープは小てつはきらいである。どこか他府県の山登り専用の山ならいざ知らず、京都の山にテープはいらないと思っているのだ。北アルプスの標識は本当に危険を知らせるものだけど、北山のテープは何のためのものなのだろう?自分が迷った時に、引き返せるようにつけていってるんだろうか?また自分が来るときのため?グループ登山の先行者?でも中には、歩いた日付と名前が書いてあるのもあったりで、なんか「俺様がここを歩いたぞ〜」的な感じのもある。まあどっちにしても、生木に針金の標識と一緒で山のゴミだと思っている。 みなさん、「中尾根」にテープはありません。しかし、道がはっきりしていますので迷うことはありません。 さて、あっさりと「大岩」についた。このまま登って「水尾別れ」の手前に出てしまえば、午前中に終わってしまいそうだが、左に折れて「米買い道」を「水尾」に向かう。
去年新聞に「米買い道」を整備・・、の記事が載っていたが、各所に看板が設置されたのと、やはり幾分かは明るくなった気がした。ただあちこちで猪が地面をほじくっているので、うっかり歩いていると足をくじきそうだ。 「米買い道」は「水尾」へ向かって若干降っているので、もったいないところなのだが、ピークを極める「登山」ではなく、「山歩き」を楽しんでいるのだから、これも良しなのだ。 「水尾」にも雪はなく、道も乾いている。これなら「岩ヶ谷」の取り付きまでも稲妻号でこれたくらいだ。「水尾」の村落を抜けた最後のカーブの陽の当たるところで、おにぎりを一個ほうばり休憩、これからはしばらく陽影になる。最近細かい砂がまじるようになって調子の悪い湧き水の場所の先、カーブミラーのある急カーブのところが「岩ヶ谷」の取り付きで、入ってすぐを左に行けば「猪ヶ谷」。
「猪ヶ谷」は最後ジープ道の地蔵山分岐、スキー場跡まで200mの看板のある場所に出る谷で、「岩ヶ谷」は神社のすぐ裏手に出る谷となる。ここらで標高は320m少し、神社下が850mくらいだから、ここからが本当の登りということになるだろうか。それにしても背中のワカンはいるんかいな?の状態で、へたしたらアイゼンすらつけることもないとちゃうか?と思っていたくらいだった。 でもさすがに谷に分け入れば、雪は残っている。質はガシガシ踏み抜ける程度で、まだまだアイゼンはいらない。木の上にも雪は乗っていなくて、爆弾の心配はなさそうだし、今日は冷え込んでいるので、午後まで爆弾は心配しなくて良さそうだ。 この「岩ヶ谷」、逆に夏だとガラガラで、浮石に乗って嫌な場所もあるんだけれど、かえって雪があると歩きやすかったりする。気を付けなければいけないのはクレパス?ぐらいか・・・。 予想していた倒木もここは少なく助かる。お正月に訪れた「梨の木谷」はポキポキだった。この杉の倒木だが、小てつの近所に住まれる「真弓」出身で現在も片手間に林業をされている方に聞くと、植えられている杉の品種が違うのだそうだ。昔の杉ではなく、育ちの早い品種が植えられていて、成長が早いその分、根も幹も雪の重みに耐えられないのだそうだ。
順調に高度をあげてきたが、600mを超えると状況は一変する。積雪は30cmくらいだったろうが、木に乗った雪が落ちてたまり、歩くところでは膝ほどになりかけて、勾配のゆるくなったところでついにワカン装着となる。 つま先の上がやわい靴だとワカンのテープで痛くなるのだけれど、新しい靴は頑丈そうだ。全然痛くないし具合がいい。ただ雪質が具合良くない。まだ締まっていなくて軽いサラサラ系なのだ。グッシとワカンが踏み抜けるし、すぐふくらはぎがつりそうになってきた。 しばらくして発案!「ワカンを蹴りこみ作戦」だ。スノーシューじゃできないだろう、アルミ製ワカンだからできる荒業。ワカンの先をわざとななめ下に向かって蹴りこみ、その後かかと部を踏みしめる。これが当たりでふくらはぎも楽だし、浮力も得られ、軽い雪だからラッセルでも苦にならず、ワシワシ登っていける。 750mを過ぎて亀岡の町が見え始めたころ、携帯のメール着信の音がした。捜査員Iからであった。愛宕に行くことは伝えてあったが、小てつは早朝出立だったし、決行メールはしないまま圏外になってしまっていた。ジープ道まで出なければつながらないだろうと思っていたが、決行している旨と現在位置の返信をする。
この「岩ヶ谷」、正月前の雪がずっと残っていただろうからわかるけど、全く人が足を踏み入れた形跡がない。ここで何かあったら、まず見つけてもらえないだろうから、場所のわかってもらえる人への連絡は最重要となる。 雑木混じりが、杉の植林ばかりになってくると、もう稜線が近くなり、りっぱなお墓のところまでくれば到着まじか、右の広い道を回り込めば、神社北ジープ道に出会う。 三角点でお昼にしようと、ワカンをはずして三角点に向かう。雪はあったが邪魔くさいので、登りはどうでもと三角点ピークを登りかけたとき、二人の男性が降りてきたので脇によけ、こんにちはと声をかけると、なんとJOEさん。 悪天予報だったので、「比良」をあきらめ、こちらにこられたそうで、「誰かと思ったけど、声でわかった。」 とおっしゃる。そう、小てつは野球部仕込みの大声である。ガッチリの重アイゼンにワカン、ピッケルまで装備され、「比良仕様」で、そのままきたから、使う場所もないし目立ってしゃ〜ないとおっしゃるから、地蔵の北っかわでもとお勧めしたが、早くきて早く帰るがポリシーのJOEさんは、今日のところは「竜ヶ岳」の分岐だけチェックして帰りますとのことで、ではまたとお別れした。 okaoka clubのメンバーの方たちの中で、JOEさんだけ山でお会いしていなかったのだが、お会いすることができた。しかし、「愛宕山」でお会いするとは・・・。この三角点付近では、以前森の旅人Mさんともお会いしたし、修学院のNさんと会ったのもここだった。やっぱり何かあるんかなぁ。 三角点広場で残りのおにぎりをパクつき、先週の残りの「琥珀色の液体」で体を内側から温める。そう稲妻号利用では、これができない。 さて降りようとして選択に迷う。アイゼンか新兵器か? 新兵器とは、捜査員Iがどこやらの登山者から仕入れてきた情報により手に入れた「スベランゾー」なるもので、ネーミングからも怪しいものなのであるが、捜査員Iはお気に入りである。全体は新素材のゴムでできていて、先とかかとに短いピンがついている。 雪道や山菜採りにとパッケージには書いてある。と、大阪からきて「樒原」の農協前に駐車してジープ道を歩いてきたというカップルが、それを見て食いついてきた。一応の説明をしていると、居合わせた他の登山者も食いついてくる。 「愛宕山」の表参道のような圧雪された道では、ひょっとしたらアイゼンよりも重宝するかも知れないし、完全に凍った状態ならアイゼンだと歯が浮いて余計に滑ることもあるし、必要な場所と不必要な場所が入り混じる「月輪寺道」みたいなところでも重宝するだろう。
京都ではケイヨーD2(もとのニックホビーセンター)のアウトドアコーナーに置いてあります。キャップテンスタッグ製「スベランゾーハード」¥998.−です。 さて、三角点を後にし、ジープ道に出ると、えらく軽装の団体が歩いていた。小学生高学年か中学生くらいか?ジープ道を地蔵の方に歩いていくし、まだあとからゾロゾロやってくる。ザックもなしで、越畑の子供かいな?と思い、一人に声をかける。
「寒いのに元気やな〜、どこ行くの?」
ジープ道でも参道でも、「スベランゾー」は威力を発揮した。これは使えます。また、靴にベルトなどの跡も残らないので良い。それにしてもすごい人だ。二つの小屋は満員である。それでも団体さんが後から後から登ってくる。 そんな団体さんの集団がゾロゾロしているのをしり目に、小てつは神社裏道にヒョイとそれるのである。この神社裏道、okaokaさんも以前歩かれていて、「なんてことはない道。」と評価は低かったと覚えるが、それは夏の話。雪の時にはまた違った趣があり、小てつはお気に入りである。ただ、「水尾道」の標識に「農林道行き止まり」とあるように、一般には通行しないようにとなっている。普通じゃない道で遭難されたら地元の人たちには、えらい迷惑がかかるのだ。
ただ、小てつはokaoka clubの読者なら大丈夫だと思って書き込む。インターネットを使って、そこまで調べるほどの方々なら大丈夫と判断する。この「神社裏道」の雪も500mを境に少なくなり、「水尾道」と合流するころには、雪はないけれど踏みかためられた凍った道になる。 貯水タンク前にはもう雪は全く無く、ただ雲行きが怪しい。帰りは「つつじ尾根」は止めにして、「旧道」を降りることにした。「旧道」はコンクートの固い道だが嫌いじゃない。高雄の「谷山林道」よりかは何となく好きな道だ。あっちは暗いからかな? 30分ほどで今朝取り付いた「中尾根の取り付き」を過ぎ、時計を見れば微妙な時間、20分に一本の電車はあるが、何せ寒い。自然と早足になり、赤い橋が見える頃には後8分。ちょっとダッシュでホームに乗れば、数人の登山者だけ、団体さんたちは「清滝」からなんでしょうね。 以上、小てつレポ 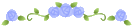
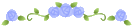
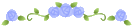
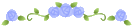
|
|||||||||||||||||||||||||||||

|

|
||||||||||||||||||||||||||||