
| 杉ノ峠古道の続きを探索しました |

|
| 雨の雲取山方面 |

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6月15日(土) 曇りのち雨 25℃ ikomochi
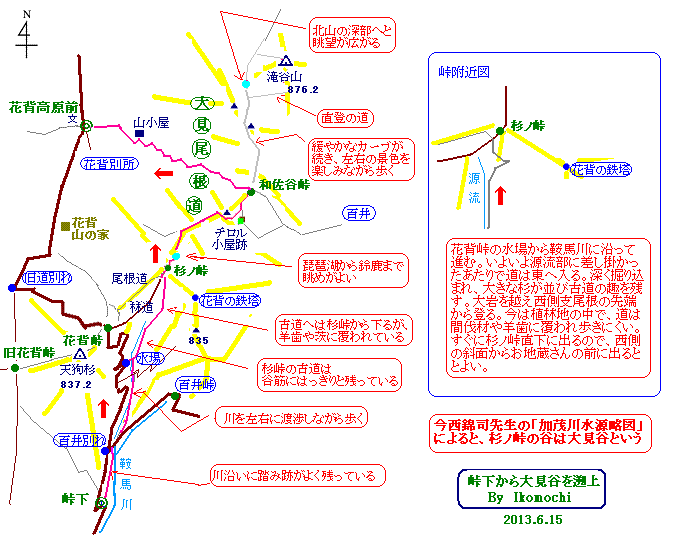
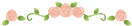
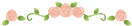
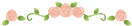
やっと梅雨らしくなってきた。午後から雨予報だが、昼間はたいしたことないようだ。本格的に降り続く前に、先日途中までだった杉ノ峠の古道探索に行こう。 貴船のことを調べようと今西錦司先生の「初登山」を読んでいたら、手製の加茂川源流域の地図などあり、花背峠周辺も詳しく歩かれている。地図には杉ノ峠の谷は「大見谷」と記載されている。 出町柳を出発するころには、ぽつりぽつりと小粒が降ってきて、車中には登山客の姿はないものの、産業大学のイベントでもあるのか乗客で満員。バスの若い運転手は鞍馬街道の離合に不慣れとみえ、京都バスの警備員の指示に従ってではあるが、あちらこちらで車待ちをする。今日は自家用車も増えているが、それにしても慎重な車さばきだ。鞍馬を過ぎたあたりで 中型の消防自動車が下ってきた。火事でもあったのだろうか。
峠下バス停に10分遅れで到着し、1人降り立った。「峠下」とは旧花背峠を指すとばかり考えていたが、杉ノ峠や新花背峠の3峠分岐を意味するのかもしれない。昔からあった地名なのかもと考えると、わくわくする。
ヒル避けを振りまきスパッツに手袋と装備よし。薄暗い杉木立の鞍馬川へと下る。ここらは広く平らな谷間で、杉の落ち葉の上にはっきりと踏み跡が続き、人が行き来しているようだ。頭上には、峠の車道がつかず離れず続く。まさかこんな谷間を歩いている人がいるとは、車中の人は気づかないかもと考えると、愉快になる。川べりを遡るとすぐに、古い橋にぶつかる。橋の下をもぐっていけないことはないが、一旦道に登った。百井峠新道だ。越えてまた川べりを歩く。
少し谷が狭まり、道形も怪しくなったりするが、歩きやすそうなところを渡渉しながら進む。苔むした岩の上を足場に渡ろうとするが、新しく買ったテクニカの軽登山靴は足元がなんとも不安定。きれいな山道をさくさく歩くには良さそうだが、どうも今日のような歩きには向いていなさそう。滑らないように足場を確かめるので時間が掛かる。 道を探し探し遡上していくと、沢幅が狭くなり、いったいどこを歩けばよいのやら。頭上を見上げると、車道にはトラックや作業車が停まり、なにか工事中らしい。前方にコンクリートの人工物が見えるのでよく確かめると、土管の上に道があるようだ。思い出した。ここはP835に向かう林道だな。沢を渡って道に上ってみた。やっぱりそうでした。サワフタギの霞のような花が咲き乱れている。
昼食にしようかと苔むした道端に座っていると、車道のほうから作業服のおじさんが一人ぶらぶら下ってきた。タバコ休憩をしている様子。こんにちは 声を掛けると、おじさん近寄ってきた。工事はなにをしているのか 尋ねると、ドコモの電柱を建てているのだとか。花背峠までアンテナが延びるようだ。 峠から鞍馬温泉までは携帯不通域。どんどん便利になっていくのでしょう。おじさんもわたしに何をしているのかと聞くので、「鞍馬の古道を歩いているんですよ〜」「一人で歩いていて熊に合わないか?」とか心配する。話すうちに、おじさんも若い頃相当な山好きで信州や比良を歩いていたそうで、熊に遭遇した話とかしばし話が弾んだ。辺鄙なところで仕事をしていると変化がないが、今日は家に帰って奥さんに話すことができたと、楽しそうに話されたのが心に残る。
小雨が降り始めたが、杉木立の中は濡れないので、雨具も着けずそのまま歩く。峠の水場辺りに来ると、水量がぐんと減り、枯れ沢になっている。水場はどうなっているか見に、車道に上ってみた。水量は半減しているが枯れることなく流れ落ちている。甘い水をポットに汲んで帰ろう。持参のお湯を空けるためコーヒーで一服。雨脚が強くなった。
水場から水のない沢を遡上。鞍馬川の源流が花背峠の直下から流れ出す辺りに来ると、深く掘り込まれた道形が沢を離れ東へと続く。先日はこの道形を見つけ出せず、へんなところを下ってきた。杉の葉が深く堆積した道の両脇には古い杉の木が並び、わああ ここってまさに街道やん と嬉しくなる。
道はゆきあたりで、大きな岩が転がっている。さてここからどう行けば?東側の大きな支尾根の急斜面はちょっと道には不適当だが、でもまあ と踏み跡を辿って上から下を眺めると、深く掘り込まれた道がくっきりと浮かぶ。道は西の小さな支尾根先端を登るようだ。行ってみると、ここにも杉の並木の名残があって、ますます嬉しくなる。あたりを探索。結局、植林地の中に古道ははっきりと残っているものの、間伐材や羊歯に覆われて歩きづらい。雨に濡れた藪を掻き分けて歩いたので、びっしょり濡れてしまった。
杉ノ峠直下から西側の草むらを上った。踏み跡があり、木にひっそりと赤いテープが結んであった。今日見かけた3つの目印。いずれも控えめに結んであり、付けた人の心を感じました。杉ノ峠の車道にがさがさと出ると、目の前は尾根道の取り付きだった。
丁度1時50分。うろうろしていたので、思いのほか時間が掛かった。このまま花背峠でバスを待つことか?それとも予定通り、和佐谷を下ろうか一瞬思案したが、えいっと大見尾根道を走る。雨に煙る道を和佐谷峠目指して走って、14時着。別所まで下り30分なので、帰りのバスに間に合うだろう。 この道は花背山の家の初心者コースらしく、きれいに整備され標識が立つ。杉林のジグザグを下る。あれれ なんか足が軽いぞ! 膝を痛める前から、下りが苦手で力が入って余計にへっぴり腰で下っていた。時には石に足を取られて、膝が痛くて冷や汗をかきながら、下っていたものだ。S先輩からは、もっとぽんぽんと足を繰り出して下れませんか?どすんどすん下るとしんどいですよ と注意されていた。
トレーニングで教えてもらった、身体の中心を感じて歩く、身体のバランスを取りながら歩く方法、少しづつだが感覚が分かってきたみたいで、最初はひっくり返りそうで怖かったバランスボールの上で腹ばいになって両手両足を上げる方法も、次第にコツがつかめるようになってきた。ぽんぽんぽん、足がリズミカルに振り下ろされ、スピードを上げても膝が痛くない。こんな感覚初めて。やったね!先生に報告しよう と、意気揚々と走り下った。 整備された杉木立の中は、雨が直接落ちてくる。すっかり濡れたが、いまさらでも雨具を着ければましだろう。きれいな沢で蛙が鳴き、野草も咲いているが、全体杉林で人工的、変化のない山道だ。 もうすぐ集落だろうかというあたりで、赤い屋根の山小屋があった。入ってみると、無人だがふわふわの腐葉土が敷かれた小道があって、大事に手入れされているようだ。小屋の向こう側には山の家があるのか、子どもたちの歓声が響く。(あとで調べたらこれが「わさ谷小屋」で、知人の父君藤原先生が建てられた有名な山小屋のようだ。かつては市内の先生方がここでの勉強会を楽しみに通ったと聞いたこともある。もう維持管理がたいへんだから、染色家か工芸家に譲ったのと伺ったことを思い出す) 山小屋の前から田んぼ道を下っていく。眼前に雲取山の山並みを望み、とても気持ちよい道だ。色鮮やかな野アザミを愛でながら、数軒の民家を通り過ぎ、バス停の元農協にたどり着いた。14時50分。無事セーフです。花背スキー場跡の道から小学生の団体がぞろぞろ下ってきた。みんなカッパ着てびしょぬれで、ご苦労さんです。
農協の陰で濡れたシャツを着替え、暖かいお茶を飲んでいると、アニーローリーが響いてきた。帰りの運転手さんは行きと同じ若い人でした。 花背峠の下りで、また上ってくる消防自動車と離合した。今日はなにかあったのか、サイレンは鳴らしていないけれど、珍しく消防車が行き来しているなあ。そんなこと考えて、翌日の朝刊を読んだら、小野村割山頂が山火事で消火に手間取ったとあった。川の水量も少なく、山の上でたいへんだったと。広範囲が焼けたようだ。空気も山も乾燥続きだったから、鎮火に時間が掛かったでしょう。登山者の不始末でないことを祈る。あの大きなブナたちは耐えただろうが、細い幹の雑木たちはどうなっただろう。 今日は古道探索を完了し、山歩きの方法も改善しと、満足の一日だった。下山後銭湯でゆっくり疲れを取り、寝る前にストレッチとアイシングを念入りにしたが、ちょっと足りなかったかなと思っていたら、案の定、夜中に足が痛むので、またアイシングした。これで痛みは落ち着きました。なかなかお勧めの方法です。
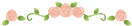
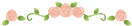
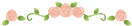
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||