
|
愛宕山〜地蔵山(NO.34)
|

|
|
雪の回廊 愛宕山から地蔵山への道 |

|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成25年3月3日(日) くもり 小てつ単独
コース: 保津峽〜中尾根〜米買道〜水尾〜岩ヶ谷〜愛宕三角点〜地蔵山〜月輪寺道〜大杉谷道〜愛宕スカイライン〜水尾別れ〜ツツジ尾根〜保津峽 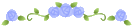
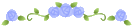
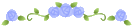
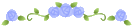
武奈や城丹国境尾根の激しい雪も「生きてるぞ〜」みたいな気合が入っていいんだけれど、ここは地蔵山のやさしい雪もいいもんだろうと、多分愛宕では今シーズン最後であろう雪踏みをしてきました。 前日2日の土曜日に嵐山にいた小てつ。見上げる愛宕には、また雪が舞っている。先週初めに降った雨で真っ黒になっていた愛宕だったが、この雪でまた雪化粧とあいなった。それではと雪の無かった正月3日に訪れて以来、2ヶ月ぶりに雪の愛宕に行ってみることにしました。 今日はJRのお世話になり、保津峽駅に7時15分着の電車で降り立つ。ホームには、寒いだろうに既に「鉄男君」がいて電車の写真を撮っている。準備は中尾根の取り付きでと、早速歩き出す。中尾根の取り付きまでは、ほぼ20分のアスファルト歩きとなる。厳重な林道ゲートを過ぎた、車道が右にカーブをするところが取り付きとなる。テープ類は無いが、踏み跡がハッキリしているのですぐわかる。
向かいにガードレールの広くなったところがあり、そこでスパッツを着け、上着を脱いで、ストックを伸ばし準備をする。最初はシダの中、明瞭な踏み跡をたどる。ひと登りすると雑木の中に入り、踏み跡がわかりづらくなるが、左手の方を注意していると、なんとなく踏み跡とわかる道が現れてくる。北に向かっていることと、登っていることを忘れずに。 どこの山でもそうだけど、ずっと登りはシンドイもの。この中尾根は登り一辺倒ではなく、時々は平坦な場所があって、息がつげるのが小てつのお気に入り。実はJOEさんも、「一度中尾根を歩いてみたい・・」とおっしゃっていて、是非どうぞとお薦めしている次第だ。ツツジ尾根を登りに使うより、ずっといいと思う。
40分ほどで「大岩」に着く。ここで大岩の左手の尾根に取り付くと、一気の登りで水尾別れまで行けて、今日の登山もすぐに終わりそうなんだけど、変態小てつは米買道を水尾へと歩いていく。ここらあたりは植林の枝に雪がのっていて地面に雪は少ない。登山者の踏み跡は無いが、BMXだろう自転車のタイヤ跡が数本残る。 大岩から水尾までは60mほど降りとなって、実にもったいないのではあるが、古道の雰囲気が楽しめる。20分ほどで到着。米買道の水尾側の取り付きは、きっと初めての人にはわからんだろうなぁと思う。水尾に8時40分着となったから、8時5分保津峽発のバスで来る方が早い。時短と体力温存したい方にはお薦め。
水尾の村を抜けると大きな擁壁工事をやっていた。道路脇の側溝に冬イチゴがあったのを思い出し、探していると今年もありました。口には入れないけれど、ほっとする。 水場を過ぎた、車道が左にカーブをするところが岩ヶ谷と猪ヶ谷の取り付きとなる。入口にチェーンの車止めが作られていたし、猪ヶ谷の方にも新しい林道が作られていた。岩ヶ谷の方はそのままの様子。今日は右手の岩ヶ谷に入っていく。
取り付き付近は標高330mほどのところ、雪は多くない。でも愛宕の南側ではここが一番雪の多いところと思うので、雪踏みにはお気に入り。でもこの季節にここを通る人は、まずいないから、何かあっても見つけてもらえないので、それなりの装備と覚悟は必要となるだろうし、岩ヶ谷がどこかわかる人に連絡が入るようにしておかなければならない。愛宕は京都北山では雪の少ない山だし、何より市内から見ても様子のわかる山。それでもコースによればワカンやシューがいるところがある。いらないと思うけど、今日も小てつはワカンを担いできた。 岩ヶ谷は古くの石組みの道がところどころ残るものの、少々あれた谷道で、逆に少し雪があったほうが歩きやすかったりもするのだが、今日は雪が少なくて歩きにくい。右岸、左岸と歩きやすい方に渡りながら詰めていく。標高500mあたりに大きな岩が見えてきて、これが「岩ヶ谷」の名前の由来ではないかと思うほど、高さ15mを越すだろう大岩が現れる。 植林から雑木、標高700mほどで、また植林となるころに稜線が明るくなってきて、もうひと登りで立派なお墓のあるところ。林道のような道を右に巻いてジープ道に合流する。やっぱり最後までワカンもアイゼンもつけず仕舞。
ジープ道は薄ら氷の上に雪が乗り、三角点の登りでは一層下が凍っている。降りはスベランゾーが欲しいところ。三角点には小てつが一番乗りで、新雪を踏んで「やっぱり冬の愛宕はこうでなくっちゃ」と雪の乗った木々をバックに写真を撮る。 ベンチまで降りて、オニギリをひとつパクつく。ここまで登ってくるとやはり寒くて、手袋を厚手に替える。久々にスベランゾーをつけて、三角点を後にし、今度は地蔵山に向かって、ジープ道を西へ向かう。竜の分岐に踏み跡は無いが、地蔵方向には数人の踏み跡がある。
今日は北部の天気が悪いようで、北山や比良の展望は無いが、振り返ると雪の乗った木々がまるで満開の桜のようで、その向こうに愛宕の鶏羽がそびえて、まるで絵になる。 地蔵に向かう道で、木の枝葉に針のように成長した氷を見つけ、写真に収める。エビの尻尾では無く、花火のようだ。きっと冷え込んだせいだろう。あちらこちらで氷の花火を見つけ写真を撮っていると、単独男性に追いつかれた。「面白いものがあって、写真を撮りながら歩いてると、遅々として進まずですわ。」と話し、先行していただく。結局、反射板ピークあたりのが、一番成長していた。
地蔵まで踏み跡があったのに、ピークに足跡の主の姿は無く、先行の単独男性は「すぐそこまでピストンしてきますから、荷物をよろしく。」と言われる。「西向地蔵ですか?」と聞くと、「そうです。」と。小てつは場所をつくって、ラーメンタイムとする。 単独男性も帰ってこられ、同じくカップ麺タイムをとられる。話すと枚方からこられ、今日は保津峽から神明峠までアスファルト道で上がり、神明峠から尾根道、ジープ道で、ここまでこられたそうだ。
去年、小てつが町内登山で使った愛宕神社まで最短時間で行ける「愛宕裏参道」は、一応関係者以外立ち入り禁止の谷山林道か、国道162号線「愛宕道」から入るかしなければいけないので、少々後ろめたさもあるけれど、神明峠からなら無余地である駐車禁止の後ろめたさはあるものの、こちらも愛宕神社まで普通1時間で行けるので、短時間アタックや足に不安のある人は神明峠まで車であがれば楽ができる。小てつ町内のHさんは、毎年正月2日に、ここから愛宕神社の御札をもらいに行かれているそうだ。 枚方の男性は、毎日日曜日になられてから積極的に各地もまわられ、百名山も、あと2山で完歩とおっしゃる。どうりで山慣れた雰囲気を持たれた方だと思った。ただ小てつの場合、百名山には全く感心がないので申し訳無く、どちらかと言うと、百の山を1回ずつ登るより、4つくらいの山を、あっちこっちから25回ずつ登る方に向いているので、話にのれず申し訳ない。 今日のコースを聞かれるので話してみるが、的を得ない様子。今日は「愛宕周辺地図」を持ってきていたので、それで解説し、せっかくなので進呈する。 それではまたどこかでと、小てつが先にピークを出立し、今日は竜には行かず、元きた道を帰る。途中で単独男性に会う。男性も氷の結晶を興味深く見ておられた。 ジープ道は朝よりも凍っている感じで、スベランゾーが有効。月輪寺道に入ると、これまた多くの人に踏まれた登山道は、テカテカ。アイゼンだと引っかかるし、木の根にも悪し、もちろん雪の少ないところの土は掘れるし、こう言う場所ではスベランゾーが一番。 大杉谷のつづら折れまで来ると、登山道にはほとんど雪は無い。2度折り返したところで、愛宕スカイライン道に入る。何と先行の足跡がひとつ。森の旅人Mさんも、先日このルートを使われたが、okaoka clubメンバー並みの変態登山者が、今日は出没したなとうれしくなる。去年訪れた時には無かった崩落場所が二箇所あった。もしや追いつくかと、ガンバって歩くが、結局誰にも会わず表参道に出る。
水尾別れで、グループがたむろしているが、小休憩だろう。脇を抜けツツジ尾根の取り付きに急ぐ。幸い表参道名物の'変なん'には遭遇しなかった。助かった。 ツツジ尾根に入って、すぐに以前とは景色が変わったことに気がついた。木につけられていたテープ類が無いのだ。実は今年正月6日に親子4人の遭難騒ぎがあり、後の報道で、迷ったのは「テープにつられ、近道と思いツツジ尾根に入ったのが原因」となっていたのだ。迷ったのは、午後から愛宕山に子連れで登るという愚行が招いたので、ツツジ尾根が悪いのではないけれど、新聞には「意味不明なテープは、遭難を招く」と書かれ、管轄警察が主体となって、対策をたてるとあった。きっとその対策で、木に巻かれていたテープ類が撤去されたのだろう。 見事スッキリとしたツツジ尾根である。テープの無い山道が好みの方々は、是非早いうちにツツジ尾根を訪ねてみられることだ。だいたい、ツツジ尾根ほど良く踏まれた山道に、テープなんて最初から全く要らないのだ。この調子で愛宕の他の山道にとどまらず、城丹国境尾根や小野村割岳の方まで、何とか外して回っていただきたいものだ。
この木にテープをつけるというのは、どこから発祥したものなのだろう?確かにガイドブックには、「木にテープをつけながら進もう!」なんて文面を見受けるものがある。しかし、北山の大先輩である金久氏や歩京さんの記述には、そんな目印をつけて歩いたようなことは書いていない。京都北山では最近やりだしたことなのだろう。だいたいビニールテープも昔は高かったし・・。山でいちいちテープをつけて歩いているより、先に進んだ方が早いと思うのだが? 中には「伏見区のU」さんのように、'俺がここを歩いたぞ〜'みたいなものもあって、何か商店街のシャッターにされた落書きスプレーと同じような気がする。正直目障り。 荒神峠まで降りてくると単独男性が休憩中で、小てつも一度ザックをおろして衣服調整をする。ここまで降りてくると暑い。男性は休憩が終わると落合の方に進まれた。珍しや・・。小てつも今度、清滝側からアタックの折に歩いてみようかと思う。 今日は保津峽に帰るつもりなので、ツツジ尾根入っていく。やはりツツジ尾根は、この季節午後にはグチョグチョになっていて、靴とスパッツが汚れてしまう。朝登った中尾根を右手に見下ろしながら、長い尾根を降っていく。
車道に降り立ち、まだ時間も早いことから、電車は20分に一本はあるので、惜しいところで乗り遅れても、次の電車までに後片付けをしていればいいやとそう急ぎもせず駅まで歩き、後片付けはホームでしようと、行きに買っておいた切符を改札に通すと、何とトンネルの中から電車の近づく音がする。いくらなんでも、このタイミングじゃ乗らないとと、ザックカバーそのまま、スパッツそのままで、14時41分発の電車に乗り込んでしまう。床を汚さないように極力動かず、ザックだけおろして降車駅までオーラを消して小さくなっていることにした・・。車掌さんごめんなさい。 今日は保津峽〜保津峽のコース取りでしたが、結構歩きごたえのあるルートでした。真綿のような雪も踏め、氷の芸術も見ることができ、満足の旅でした。
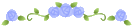
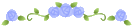
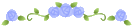
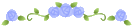
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||