
| 大文字山 (中尾城址~中尾滝~幻の滝)//東山 2017.01.06 |

|
| 平日だが約30名のハイカーで賑わう △大文字山の山頂 |

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017.01.06 (土) 曇り 哲、道
コース: ・銀閣寺大文字山参道~行者の森(中尾城址への登山口)~中尾城址西尾根~中尾城址~鞍部分岐~中尾滝分岐~中尾滝~滝上から支尾根~分岐を左へ下る~谷出合(幻の滝)~谷筋を登り折り返して支尾根を登る~支尾根分岐(出合坂)~左へ支尾根を登る~階段分岐出合~大文字山登山道出合~△大文字山 ・△大文字山~北の植林地を下る~階段分岐出合~支尾根分岐(出合坂)~西の谷へ~西の支尾根へ~横道~中尾城址への尾根出合~中尾滝分岐を左~中尾城址手前の鞍部分岐~堰堤~大文字山登山口~行者の森
注意:
◆大文字山周辺には登山道以外にたくさんの古道(作業道)があります。これらを辿るたくさんの登山コースがあります。また尾根や谷筋にたくさんの道があります。支尾根を登って行くと△大文字山へ通じていることと、中尾滝や幻の滝は大文字山登山道の東にある事を頭に入れておくと、迷っても簡単にエスケープできるでしょう。簡単な山ですが地形図やコンパスの利用をお勧めします。 
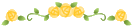
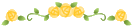
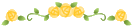
【 銀閣寺行者の森~中尾城址~中尾滝~幻の滝~△大文字山 】
「あ~、比良や北山に雪がない。正月明けは毎年、積雪の情報収集に大見尾根へ出かけているが、今年は暖冬で行くまでもない。 「それじゃあ!」と昨年末に出かけた大文字山の宿題「中尾滝」「幻の滝」を片付けに出かけることにする。とはいっても大文字山なので小ザックでハイキング、こんな歩きが続けば次の登山がキツクなるだろうと。目的地は滝なので谷筋にあり、大体の場所は予想できるので、地形図とコンパスで進み、できるだけ古道を歩くことにする。 市バス銀閣寺道で降り銀閣寺から大文字山登山道へ向かう。朝鮮学園への分岐の所に「行者の森」の石碑を見る。谷沿いの大文字山登山道を進み駐車スペースを過ぎたころで、分岐から100mも進まないうちに、石垣が切れたところで左手の植林地へ入って行く踏み跡を見る。ここが中尾城址への登山口である。9時45分、遅いスタートとなる。
早速進入して北東への支尾根を登って行く。足元には踏み跡が続き、支尾根の登りなので迷うところはない。15分登って標高220m過ぎの小ピークに着き小休止する。尾根は小ピークから南東へ下って行く。右手に斜面の崩壊個所が修復され、立ち入り禁止の表示を見る。
鞍部まで下ると、今度は急斜面を登り始める。標高250m付近から足元に階段を見て、それを登りきると南北に伸びる尾根に乗る。これが中尾城址のある尾根である。この尾根を右にとると、標高280m付近で尾根は少し広がる。この付近が中尾城址で木に名板を見る。
中尾城址付近は快適な尾根が続き、緩やかに南へ下って行く。中尾城址から100mも下ると、標高260mの鞍部の分岐に着く。この分岐を西に下れば大文字山登山口上にある堰堤付近に出そうなので、「帰りにでも歩いてみよう!」と哲郎。
その鞍部から道は尾根を避けて左手に巻いて行く。少し進むと分岐に出合う。右の尾根へ上がって行く道をとれば、最後は大文字山登山道に出合う。今日は左にとり中尾滝へ向かう。 道は支尾根を下って行き、最後は右に下って行くと谷筋に出合う。踏み跡は薄くなっているが、谷上に道はなく、道はここで折り返し谷沿いを下って行くと谷に降り立つ。
右手に谷を渡ったところに道が見えるので、「滝はこの谷になさそう~!」と、谷を渡り道を辿って東へと進んで行く。 しばらく横道を歩いて行くと目の前に分岐を見る。右は谷に沿っているが、左の道は谷へ降りて行くので、「ここだろう!」谷へ降りて行く。よく見ると傍の木に【→ 中尾の滝】と書いてある。
谷へ降りて行くと、目の前に小さな滝を見る。予想外に小さく「これか~!」と。滝を一見しすぐに降りて来た分岐に戻り、古道をさらに奥へと進んで行く。古道はシッカリしていて谷上を進み、谷へと下って行く。 滝上で谷に出合う。幻の滝はこの谷の上流にあるようなので、この谷を辿って行っても良いが、「どうしよう!」と周囲を伺う。「これ、古道?」と、右手に登って行く道を見つける。今日はなるべく古道を歩くことにしているので、この道を辿ることにする。
道はすぐに支尾根に乗り南へと登って行く。どんどん登って行く古道、予想に反して谷から離れて行き、支尾根を登って行く。支尾根の登りが続き、古道は谷へと下って行かない。「幻の滝へは必ず古道があるだろうが、この道で滝へ行けるやろか!」と心配する哲郎。 標高320mを過ぎたところで右の谷から登ってくる道に出合う。この道は二人が登って来た道より踏み跡が濃くハッキリしていてよく利用されているようなので、「この道も、帰りに歩いてみよう!」と哲郎。 中尾滝から支尾根を登って来た道をすすんで行くと、やっと下り始め一安心の哲郎、「谷に降りたら幻の滝があるだろう!」と。
古道を下って行くと谷に降り立つ。枯れ谷だが広々としている。「この付近に滝があるようだ!」と周囲を見渡す。大文字山へはこの谷筋を南へ登って行くようで、「穏やかに登って行くので、こちらにはないだろう!」と下流を探すことにする。 谷の東側に踏み跡を見つける。その道を50mも進むと炭焼窯跡を見て、崖に突き当たり、その横の木に「幻の滝」の名板を見る。崖を見ると水が流れた跡があり「これが幻の滝か!」と哲郎。滝の下には流れていく谷はないので、大雨が降った時に崖上から水が流れるようで、とても滝とは言えないようである。
「な~んだ、崖か!」と、二人はすぐに谷筋の分岐まで戻り、△大文字山へ向かうため南へと谷筋を登って行く。道はハッキリしていて標高330mを過ぎたところで、左へ折れ折り返すように左手の支尾根へと登り始める。道は緩やかに登って行き、標高360m付近で支尾根にのる。
この分岐の木に「出合坂」と書いてある。支尾根を北へ下る道は「→熊山コース」とも書いてある。△大文字山は南にあるので、この支尾根を登って行く。 道なりに進んで行くと右手に登って行く階段を見る。上にも下にもロープが張ってあり、二人が歩いてきた道を横断するルートがあるようだ。古道は先へ向かっているようにも見えるが、今日はこの階段を登ってみることにする。
階段が過ぎると、道は落ち葉で不鮮明になる。薄い踏み跡を辿って登って行くと右から登ってくる道と合流する。大文字山登山道ではないが、ハッキリした踏み跡で良く歩かれているようだ。この道の探索はまたにして、そのまま登って行くと、すぐに大文字山登山道に出合う。 左にとり登山道を登って行くと、すぐに△大文字山の山頂に着く。12時10分なので、行者の森登山口から2時間30分かかったようだ。 今日は平日だが、正月明けで天気が良いので、約30名のハイカーが昼食休憩中である。昼食は降りてからと、用意していなかったが、予想以上に時間がかかり「遅くなった!」と非常食のバーを取り出し、京都市街地を眺めながらこれを頂く。
【 △大文字山~幻の滝~横道~中尾城址への尾根~大文字山登山口 】
10分休憩して下山を始める。下山ルートは途中で出合った分岐からの道を確認するため幻の滝まで下ることにする。山頂からはベンチ裏の植林地をジグザグに下って行く。少し緩やかになった所から正面に比叡山が見え、ロテルド比叡の建物がハッキリ見えてくる。
比叡山を見ながら下って行くと、道は左への横道に変わる。だれがしたのだろうか石が積んである。これと同じものを幻の滝から谷筋を詰めて行くときに見ている。少し進むと登りで使った階段に出合う。山頂へは階段を登らず真っすぐ進んでも良かったようだ。 「右手のロープがある下って行く道は、何処へ行くのやら?」と思ってしまうが、今日は真っすぐ支尾根を下って「出合坂」へ向かう。出合坂に着くと左の道をとり谷筋へ下り幻の滝の分岐へ向かう。
谷筋まで下って行くと、折り返すように谷を下って行き、幻の滝の分岐に着く。ここから左手の道を登って行き支尾根に乗り、「行き」で確認した分岐に着く。支尾根を真っすぐ下って行くと「中尾滝」だが、帰りは左の道を歩いてみる。 尾根道から左の道へ入り、西へ下って行く、最初は溝状だった道も、すぐに緩やかになり谷へと下って行く。広い谷間に降り立ち少し下って行くと、標高300m付近で道は左の斜面を登って行く。
道を標高差10mも登ると支尾根に乗り、そこから道は斜面を巻いて行く。平行に進んで行く巻道が終わると、尾根の古道に出合う。よく歩かれている道で、目の前の木に「←大文字山三角点」と書いてあるので、中尾城址から△大文字山への尾根のようである。 左(南)にとれば大文字山なので、この分岐を右(北)へ進み中尾城址方面へとる。すぐに、先日火床東の谷筋からカサを見て登って来た分岐に出合う。あとは先日歩いた尾根道を、道なりに進んで行く。
道は尾根から右に少し下って行き中尾滝分岐に出合い、左に巻いて行くと標高260mの中尾城址手前の鞍部に着く。今日はこの鞍部から西へ下って行く道を歩くことにする。 道はハッキリしていて、谷沿いの植林地を下って行く。そのうち右前方に堰堤が見えてきて、最後は左からの谷の堰堤の上に出る。
道には階段が設けてあり、難なく堰堤下に降りることができる。右からの谷を渡ると、大文字山登山口上の堰堤を見る。この右端を通って登山口に出る。 今日は「やれやれ」ということもないハイキングであったが、色々と楽しませてもらい「楽しかった!」と道子。
登山道の湧水で用具を洗い、「昼食だ!」とGOSPELへ向かう。道子が覗くが「1/7からだって!」と。閉まっているので手前の「おめん」へ寄る。もう14時頃だが、たくさんの観光客で賑わっている。うどん+ビールをおいしく頂き、心地よくなったところで二人は帰路に着く。 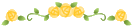
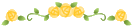
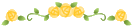
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||