
| 大文字山(疎水公園~楼門の滝への脇道) 2020.12.29 |

|
| 大文字山登山道からちょっとした脇道へ進入してみると 最後は整備された谷間にでて鹿ケ谷道に出合う |

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020.12.29(火) 晴れ 哲、道
コース: ・JR山科駅~疎水公園~諸羽山~白岩~P261~陰山~鉄塔1~鉄塔2~滋賀県境尾根出合~P381~雨社~大文字山~(A-16)手前で左の脇道へ進入~広い谷間~鹿ケ谷道出合い(彩りの森再生プロジェクトの案内柱)~楼門の滝上の俊寛碑(トレイル【46】~楼門の滝下~鹿ケ谷出合(トレイル【47-2】)~霊鑑寺(トレイル【48】)~錦林車庫バス停
案内:
◆山科疎水公園から滋賀県境尾根への道は2018年の台風の倒木処理が進み問題なく歩くことができます。県境尾根の倒木も処理され迂回するようなところはもうありません。 ◆大文字山から火床へ下る登山道のA16手前から左へ緩やかに下る脇道があります。道はハッキリしていますが、最後は植林地に出合い道は怪しくなります。左手の谷間を下っていくと楼門の滝上の鹿ケ谷道に出合います。 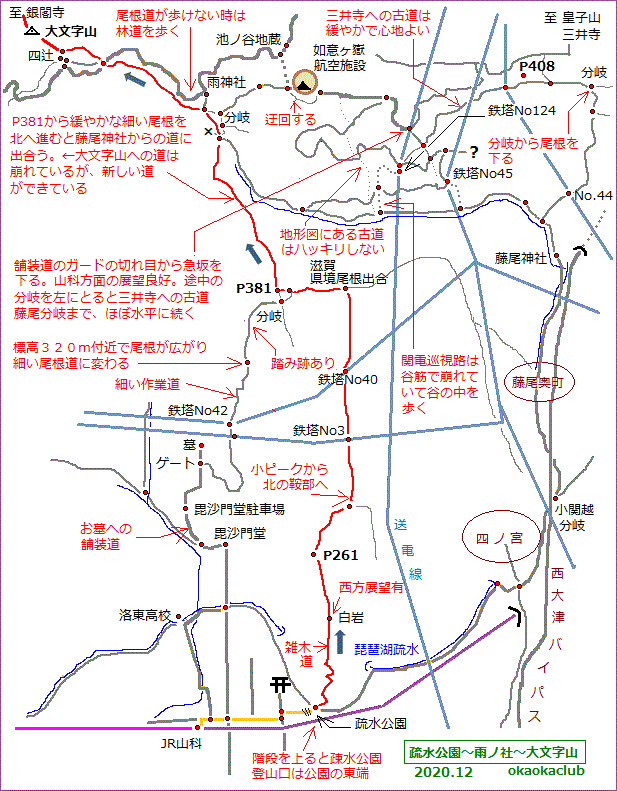
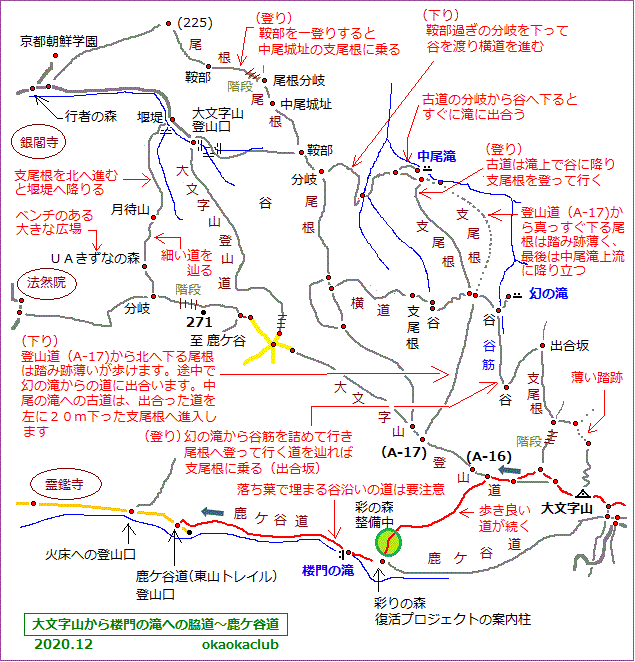
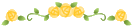
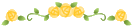
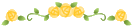
毎年年末の登山は大文字山、足慣らしに出かけることにする。 JR山科駅で降り、今日は疎水公園から滋賀県境尾根へ登ってみる。このコースは2018年の台風の倒木調査で出かけたのが最後、倒木で通れない状態だった県境尾根はどうだろう?と2年ぶりに出かけることになる。 JR山科駅から北の住宅地に出てJR沿いに東へ進んで行く。突き当たったところで左にとると諸羽神社の鳥居が見える。すぐの細い道を登っていき階段を上るとと疎水の散策路に出合い、その奥に疎水公園(諸羽ダム跡)を見る。公園の東端が登山口である。
低山だがスパッツを付け出発する。最初は急坂、足元は落ち葉で滑りそうだがすぐに斜面の横道に変わる。この付近では低山ながらの細い脇道をたくさん見かけるが、一番しっかりしている道を取ればよい。道を間違っても登っていけば最初のピーク諸羽山に着くので問題はない。 右に巻きながら登っていくと、直角に左に折れ斜面を登り始める。諸羽山まではウラジロの間の急斜面が続き、登るにつれ細い雑木が増えてくる。
25分登って最初のピーク(諸羽山)に着く。ピークには丁寧な山名札が木にくくってあるが、木を痛めるので哲郎は嫌いだ。このコースは滋賀県境尾根へのメインコースなので、この名札が続く。 少し下ったところで道端に岩を見る「白岩」と表示してあるが白くは見えない。ここから西側が開け眼下に洛東高校が見える。少し下ってから一登りしてP261に着く。このコースには小ピークが続き、いい運動になるようだ。
P261を過ぎると尾根は東よりに向いていき陰山へと進む。所々で倒木処理の残骸を見るが、大きく迂回するようなところはない。植林や疎林が続き・・・、見るべきものはなく黙々と歩く。 緩やかになり細い雑木を通り抜けると陰山と言うピークに着く。このピークで尾根は分岐しているので北の尾根を取る。ここで3人の家族連れに出会う。急坂を下り緩やかな鞍部を過ぎると、県境尾根へとユックリ登っていく。
この尾根には送電線が2本横断しているので、尾根道にたくさんの関電マークを見る。この関電巡視路は遊べそうだが、今日は真っすぐ県境尾根へ向かう。 2本の送電線鉄塔を過ぎ、真っすぐ北へと登っていくと滋賀県境尾根に出合う。ユックリ歩いたのか登山口から80分である。左にとりP381へ向かう。
台風後は100mの間大量の倒木で登山道は通れなかったが、今はすべて処理され難なく歩いていくことができる。尾根を西に進み最後はシダの中を一登りするとP381、ここで毘沙門堂裏道と出合う。 ここからは雑木が続く穏やかな道、心地よく歩いていると前方からの登山者に出会う。「早い出発やな~」と思ってしまうが、よく考えると我々の出発が遅かっただけのようだ。雑木の尾根は心地よいが、常緑樹が続き「落葉樹がもっとあればな~」と思ってしまう。
北西への尾根は標高400m付近から北へ向く。左手から登ってくる藤尾神社からの道に出合うと滋賀県境尾根は終わる。東西に連なる尾根に乗ると下に雨社が見える。ここまで登山口から120分である。尾根を左にとり大文字山山頂へ向かう。 細い尾根道には倒木が続くが倒木処理され難なく歩くことができる。林道に出合うと、これを横断し尾根道で山頂に向かう。山頂に近づくにつれ出会う人が増えてくる。12時10分に山頂に着くが、今日もたくさんの人が昼食中、二人はすぐに発つことにする。
今日は火床から法然院へ下ってみようと登山道を下っていく。雑木の急坂が終わり緩やかに変わったところで左へ下っていく道を見る。「急坂なので」と見送ると、そこから20m進むと左へ緩やかに下っていく脇道を見る。A16標識ピークの手前である。 「今日は楽しみもなかったので」と、この脇道を下ってみることにする。緩やかに斜面を巻いていく道は地形図に記載はないが、植林の作業道にしてはしっかりしているので古道のようだ。
斜面を巻いていた道は支尾根を下り始める。南の方へ進んでいるので鹿ケ谷道へ向かっているような気がする。支尾根を下っていると突然道は右の斜面を下り始める。
1,2分斜面を下ると植林地に出合う。「植林地は倒木がいやだな~」と思っていたが、倒木は処理されているので、この道は良く歩かれているようだ。 植林地を進んで行くと、すぐに前方が明るくなり広い谷間に出合う。道は前方の尾根に続いているようにも見えるがハッキリしないので、今日はこの広い谷間を下ることにする。
谷間にははっきりした道はないが踏み跡を辿って下っていく。谷間は整備され左右にネットで囲まれた幼木がたくさんあるので、この一角は何かをしているようだ。 下っていくにつれ谷間は広くなり、前方に植林が見えてくる。その植林の手前で道に出合う、「鹿ケ谷道だ!」と。そこに「トレイルの標識の柱が」を思ったら、「四季・彩り再生プロジェクト/京都市」の案内である。
出合った道を西へ下っていく。二人はこの道が20数年ぶりなので、全く記憶がない。谷沿いの道を3分進むと、目の前に大きな岩とトレイルの標識【46】を見る。よく見ると、これは岩ではなく石碑の裏側であり「俊寛碑」とある。
楼門の滝はこの下にあるようだ。右に下っていく道も見るが、今日はトレイル道に従って下り久し振りに滝を見ることにする。滝は水量少なく圧巻とはいいがたいが、ともう少し下ったところからカメラを向けるが倒木や枝が滝下に堆積していて残念と言うことになる。 この付近の斜面は急勾配で大岩がゴロゴロ、「こんな斜面に降りてきたら大変だ、大文字山にもこんなところがあるのだ」と思ってしまう。 滝見物は終わりトレイル道を下っていく。しばらく谷上の細い道が続くが落ち葉で埋まり滑らないように注意して歩く。途中で「お腹がすいた」と道子、小休止し朝買っておいたケーキを食べる。「別に急斜面の上で食べなくても」と哲郎。
山の中、谷の反対側に小屋が見えてきて、小屋と思っていたら住民が見えてきて、そういえば「谷沿いに家があった!」と昔を思い出す。 トレイル道登山口【47-2】に降りてくる。細い道の脇に民家、お寺?お宮?・・何やらよくわからない建物が続く。民家が並んでくると右手に霊鑑寺、ここにトレイル【東山48】の標識を見る。ここから錦林車庫バス停へ向かう。 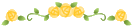
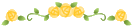
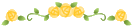
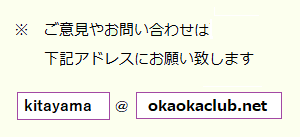
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||