 京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
 京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

北山を歩いているようだ!と谷筋を下っていく




|

|
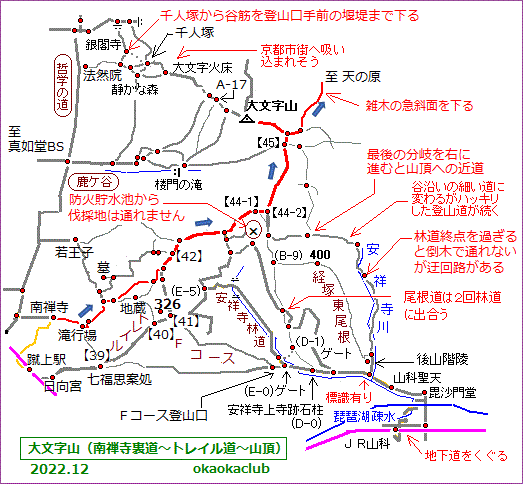
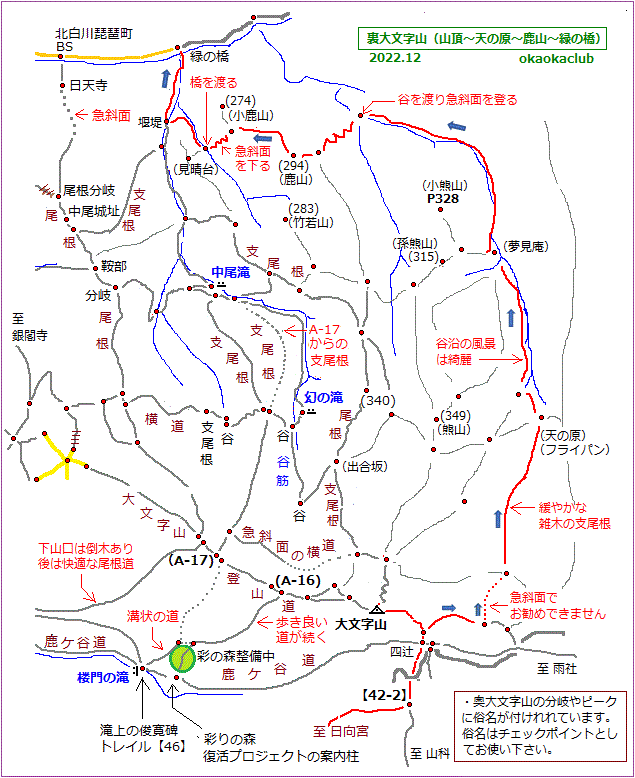



今日はゆっくりの起床、「今日だったら、空いている」と道子、これからだと大文字山か天王山、大文字山を散策することにする。
9:45に地下鉄蹴上駅に着く。駅を出て右に下るとすぐにインクライン下のトンネル、それを通って南禅寺へ向かう。初冬の南禅寺は年末とあって観光客は少ない、寒いからかも知れないが。下着とズボンは冬仕様でも寒いのは寒波の影響だろう。
 |
 |
| 蹴上からトンネルを抜け南禅寺へ | 疎水橋(水路閣)を潜って |
疎水橋(水路閣)を潜って谷沿いに登っていく。右手の谷に流れを見ないので、最近雨が降っていないのだろう。階段を登っていくと滝行場に着く。滝に細い流れを見て滝上へ上がり、谷を渡ると若王子へ向かう道に出合う。
 |
 |
| 水路閣を潜って谷沿いに登っていく | 滝行場に着く |
谷沿いの道を200m余り進むと道に倒木を見て右手に谷間を見る。ここが地蔵道(左右の分岐に地蔵がある)の入口、早速小さな谷を渡り谷沿いに東へ進む道を進んで行くと150m程で左手に石組みの小さな堰堤?を見る。
 |
 |
| 滝上の谷沿いの道を歩く | 右手に谷間を見る |
その手前、谷の右岸の植林地に道のようなものを見る。「これ、作業道?」と、今日はここから登ってみることにする。登るにつれ足元は道らしくなり一安心する。
 |
 |
| 地蔵道を進むとすぐに堰堤が | 小さな谷横を登っていく |
道は谷沿いに登っていき、途中で先日尾根の先端から登った尾根に出合う。そこから少し登り始め地蔵からの道に出合う。「やれやれ」と後はユックリ登っていき東山トレイル道に出合う。
 |
 |
| 登るにつれ足元は道らしくなり一安心 | 東山トレイル道に出合う |
トレイル道を山頂へ向かう。今日は寒いのでハイカーに出合わない。11:25大文字山に着く、山頂には3名のハイカーが休憩中だが、風が強く寒いので、引き返し風がなく日が当たるベンチで昼食とする。
11:50昼食も終わり雨社へ向かう。四つ辻分岐から四つ辻に降りずに真っすぐ尾根道で雨社へ向かうことにする。左手に冬枯れの雑木林を見て、少し登った所で左の雑木にテープを見る。地形図に北へ下っていく破線の道を見るが、それはもう少し先のピークなので違う、「このテープは?」と気になる二人。左手にはいつも昼食を取っている山頂東の雑木林が見える。
 |
 |
| 今日はひっそりとした大文字山 | 左に山頂東の雑木林が見える |
今日は雨社から疎水公園へ下るのを止め、このテープから北斜面を下ることにする。歩いてきた尾根道から少し北へ進むと、急に下り始める。その勾配はきついので、ゆっくりと下ることになる。
 |
| 急坂の雑木林を下る |
下るにつれ勾配はさらにきつくなり、ただ斜面を見ながら注意してき歩き、前方、左右は雑木で何も見えないので、どの方向に下っているのか分からなくなる。やっと横道のようなところに降り立つ。道子はスマホを見て「標高390m付近!」と。
 |
| 横道に出合う |
標高400m付近には山頂北に横道があるので、この横道はその延長かもしれない?。哲郎は右に横道を進んで見ると谷の源頭まで続いていた。道子の待つところまで戻って、「今日は降りてきた尾根の延長を下ってみよう!」と北の支尾根を下り始める。
地形図には北へ下っていく小さな支尾根がたくさんあり、GPSがないのでどの支尾根を下っているかは特定できない。下るにつれ勾配はどんどん緩くなる。右手の谷間も歩きたいような谷、「次はあの谷をあるいてみよう!」と見ていると、そこにいた鹿が東の尾根へ消えていく。
 |
 |
| 今日は降りてきた尾根の 延長を下ってみよう |
右手に谷間が見えてくる |
左手の谷間には綺麗な雑木が続き・・・、そんなことを思っていると広場のような谷間に降り立つ。「ここは何処だろう?」と哲郎、大体の所は分かるのだが低山で標高差も少なくこの谷間が特定できない。右へ進む道も見る。右に尾根を越えると池があり、その先には比叡平へ向かう道があるだろう。目の前の谷筋を下っていこうか?どうしよう!と思案していると一人の女性が谷間を登って立ってくる。
 |
| 前方に雑木の谷間が見えてくる |
「すみません、ここは何処でしょうか?」と哲郎は地形図を差し出す。「地形図では分かりません!」と、彼女は持参している地図を取り出して説明してくれる。その地図には分岐等のポイントに俗名がたくさん書いてある。
「ここはフライパンです」と我々の後ろを指さす。そこには正しく「フライパン」が転がっていて、近くの木に「天の原」の標識を見る。「フライパン」は北山で呼ぶ「ヤカン」のようなものだ!と哲郎。彼女はこの付近の説明をしてくれるが、「熊山・鹿山・二段の滝・メガネ・・・」と分からない単語が並ぶ。
 |
 |
| 「フライパン」が転がっていて | 「天の原」の標識を見る |
彼女の地図を覗いてみると「・328」が記入してあり、それを見た哲郎はここのポイントが特定できた。二人が下ってきた支尾根は良く歩かれているルートではなかったようである。どうやら谷筋が歩けそうなので、東の比叡平方面を止め谷を下っていくことにする。彼女にお礼を言い二人は谷沿いを歩きはじめる。
谷の東に続く尾根にもルートがあるようだが、この谷道も奥大文字山の東の端で歩く人は少ないようで誰にも合わない。谷筋の風景は京都北山の縮図のようなところで、「良いところだ!」と気にいってしまう。
 |
| 「天の原」から谷沿いを歩きはじめる |
 |
| 緩やかな谷間は心地よい |
15分余り下っていくと谷間は狭くなり1本の倒木が邪魔をするが赤〇マークで「ここを歩け」と案内してくれる。倒木を過ぎると谷に流れを見るようになり谷横を注意して歩くようになる。谷横に踏み跡が無くなっても歩ける所を探しながら下っていくと、前方が開け谷分岐に着く。「天の原」から30分であった。分岐の対岸には丸太のベンチがありその奥の斜面に階段を見る。
 |
| 前方に谷分岐をみて対岸に階段を見る |
 |
| 丸太のベンチから下ってきた谷を見る |
この谷は白川へ流れているが、谷口の山中越えへ白川を渡る橋は「確か通行禁止だった」と哲郎。(以前白川を渡る橋をGoogleで調べた時、橋の入り口に柵がしてあった)。この付近のコースが分からないので、目の前の急斜面の階段登ることにする。
 |
| 急斜面の階段登る |
これでもか!という急斜面に強引に丸太の階段がジグザクに作られピークへと続く。標高差70m登ると平らになり木に「南は大文字山」と書いてある。真っすぐ西へと進んで行くと「鹿山」という標識を見る。こんな俗名が書いてあっても俗名入りの地図を持っていない人には余り役に立たず、標高でも書いてある方が役に立つだろう。
 |
 |
| 階段は登るにつれ緩くなる | 「鹿山」という標識を見る |
この尾根を下ることにし北へ歩きはじめると、小さな標識に西の谷に下る道が2本書いてあり、それを下ることにする。1本目の下山口は見過ごしたのだろうか?西へ下っていくと左手に谷に下る階段を見る。これを下ることにする。
 |
| 左(西)の谷への階段を下る |
2分下ると谷に出合い手前にテーブルと対岸に渡る橋を見る。14:00「天の原」から約1時間かかったようである。この谷は緑の橋からの谷の支流で、ぐるりと斜面を巻いていくと緑の橋からの谷に出合うが、右手の下流には倒木を見る。橋を渡ると階段があり、ここも登っていく。
 |
| 橋を渡り階段を登る |
階段はすぐに終わり、「谷沿いを歩く?」いや左手の斜面に登っていくルートが続いていてソバの木に「見台」と書いてある。とりあえずそこへ登ってみる。細い踏み跡が続き支尾根に乘ると左手に階段を見る。
「見台って見晴台か!」そちらへ登っていくと緑の橋から遠ざかってしまうので進行を止め登ってきた細い道を下っていく。谷上まで戻って下を見ると谷沿いに踏み跡を見る。「道あるやん!」と谷沿いの道から植林地を巻いて緑の橋へ向かうことにする。
 |
 |
| 登っていくと見晴台だった | 谷に戻って谷沿いを歩く |
枯れた「琵琶の滝」の横を通り、西へ巻いていくと前方に緑の橋からの谷に堰堤を見る。堰堤を渡り登山道に乘る。我々が歩いてきた道は、「中尾の滝」へ向かう途中で、「左手の植林地にある踏み跡は何処へ行くのやら?」と思っていた道であった。
 |
| 堰堤を渡り緑の橋へ向かう |
「あ~やれやれ!」と谷沿いを緑の橋へ向かう。やっとたどり着いた道の途中に冬紅葉を見て「綺麗だ!」と思ってしまう。橋を渡り山中越えを下っていく。北白川琵琶町バス停、残念だがこの時間にバスがないので北白川仕伏町まで歩くことにする。
 |
 |
| 冬紅葉を見て緑の橋へ向かう | 緑の橋を渡り山中越えへ |
白川沿いの道にはまだ紅葉が残っていて、それを楽しみながら下っていく。仕伏町バス停で「バス出たところや!」と、同じ3系統だが「京都芸大からやってくるバスに乘ろう!と北白川別当町バス停へと歩いていく。
今日は雨社から疎水公園へのルートを変更し、奥大文字山を楽しんだが、東端の谷を歩いたので、これで奥大文字山のハイキングコースの全貌が理解できたような気がする。でも低山の尾根や谷はハッキリせず迷いやすいので注意して奥大文字山の散策を楽しんでください。
 |
| 白川沿いに鮮やかな冬紅葉 |



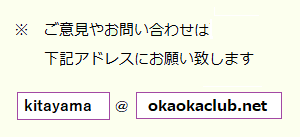

|

|