 京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
 京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

山椒谷を下っていく




|

|
注意:
・桟敷ヶ岳裏の山椒谷は一部危険なところがあります。初心者だけで出かけないようお願いします。



5月連休、明日から子どもや孫たちが次々にやってきて・・・・、二人の5月連休は今日で終わる。
何時ものように桟敷ヶ岳周辺を散策し春の野草を楽しむ。今年は1週間早い春の花だが今から咲く花は例年通りとなるだろう。今回のレポ、紀行文は止め出合った花を紹介します。
 |
| アシウテンナンショウ |
■ アシウテンナンショウは葉が1個で小葉は5個(まれに7個)。形状がよく似たヒロハテンナンショウは仏炎苞が小さく緑色なので分かる。マムシグサの仏炎苞(花)の位置は葉より高くなり、葉は2個で小葉は7以上。
 |
| ボタンネコノメソウ |
■ ボタンネコノメソウの花は茶褐色。
 |
| チゴユリ |
 |
| エンレイソウ |
■ 花が白いものはシロバナエンレイソウ。
 |
| フデリンドウ |
■ 花はハルリンドウより少し小さい。ツボミが筆の穂先のよう→フデリンドウ。



 |
| フタバアオイ |
■ 茎は地をはって伸び葉が2個対生する。花はそこに1個つく。
 |
| ヒトリシズカ |
■ 咲き終わった群生の傍に咲く、見頃を過ぎた最後の花でした。
 |
| イチリンソウ |
■ ニリンソウより一回り大きな花なので遠くからでも良く目立つ。
 |
| イカリソウ |
■ 群生の中に咲いていた最後の花でした。
 |
| ジシバリ |
■ ニガナ属なのでハナニガナやノニガナ等に似るが葉が全く違うので、区別できる。



 |
| キンキエンゴサク |
■ 花の窪みの周りが白いので、キンキエンゴサクと分かる。
 |
| キランソウ |
■ 大群生で咲くと斜面が青一色に染まる。
 |
| ミヤマハコベ |
■ 春の七草の一つ「ハコベ(ミドリハコベ)」はなかなかお目にかかれないそうです。茎が赤みを帯びているのがコハコベ。ミヤマハコベの茎は円柱形で、片側または両側に毛が生える、花はハコベの倍の大きさがある。ハコベの仲間は多く区別しにくい。
 |
| ムラサキケマン |
■ 黄色い花はキケマンで、最近余り見かけない。
 |
| ムラサキサギゴケ |
■ ムラサキサギゴケは匍匐茎を伸ばし横に広がっていく。茎が上に伸びて花を付けるのがトキワハゼ。上唇は2裂して尖ってはいないで丸みを帯びていて反り返りが少ないのがトキワハゼ、ムラサキサギゴケは花の上唇は尖って2裂し、反り返っています。と言っても両者の区別は難しい。



 |
| ニリンソウ |
■ 2個の花を付けるのでニリンソウだが1個や3個もある。それらは同時に開花しないので春先はほとんど咲いているのは1個。花弁はなく花弁のように見える白い部分は萼片で5個。多年草で地下茎で増える。
 |
| ラショウモンカズラ |
■ 花冠は紫色で下唇の中央裂片は大きく下方に反り返り紫色の斑点がある。写真は下唇が反り返る前。
 |
| シャク |
■ 川辺に咲く小さな白い花は種類が多い。花弁が5個で、花序の周囲に咲く花の外側の花弁が大きいのはシャクの花。
 |
| タチネコノメソウ |
■ 蒴果の多数の種子はほとんど散っている。
 |
| ツルカノコソウ |
■ 花の下の葉の一部が左右に2枚伸びているのでツルカノコソウと分かる。



 |
| ウラシマソウ |
■ 長い付属体が長く伸び浦島太郎の釣り糸のようだ→ウラシマソウ。
 |
| ヤマルリソウ |
■ 茎の先に総状花序を出し、次々に小さな青紫色の花を咲かせる。これが可愛い!
 |
| ヤマシャクヤク |
■ 今年は開花が早く見頃を過ぎていた。



 |
| 岩壁を過ぎるともうすぐ林道終点へ |



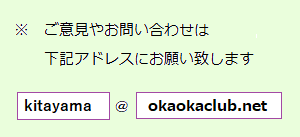

|

|