 京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
 京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

半国高山 山頂広場は標識と三角点があるだけで展望なし




|

|
日程:
・2025.1.23 (木) 晴れ 哲郎・道子
コース:
・杉坂口バス停(9:15)~フットサルコート~供御飯峠分岐~供御飯峠~峠北尾根~P534~尾根下の岩谷林道支線~林道支線終点~半国高山~林道支線終点へ戻る~林道支線を下って岩谷林道へ降り立つ~岩戸落葉神社~小野郷バス停(12:35)
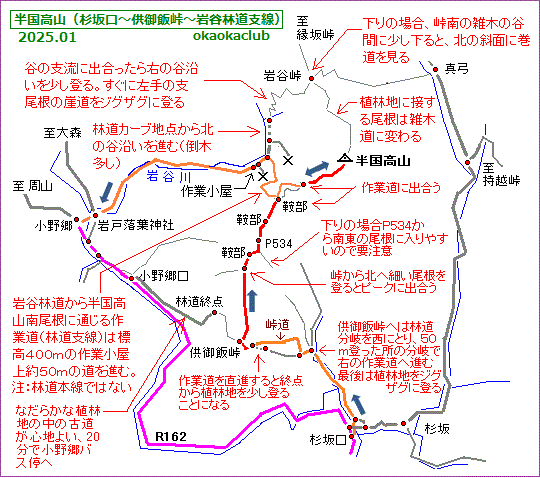



インフルエンザの後遺症も治まってきたので、今日は半国高山の尾根を愉しむことにする。半国高山へは京都駅からの周山行きのバス始発便では時間が余ってしまうので2便を利用している。最近この便の発車時刻が10分遅れ+渋滞で数分遅れるので、杉坂口バス停の到着時刻が以前より15分程度遅れている。これに年々歩きが遅くなり、帰りの小野郷12:58発にはギリギリとなる。
今回元気よく歩けると問題はないが、山頂到達が遅れた場合も考えておく。予定の下山時刻より遅れたら、時刻により【速足で下山する、また岩谷峠へ向かい真弓に下山し持ち越し峠を越え「もくもく号」を利用する、大きく遅れたら次のバスに変更する】等、計画表を修正する。
でも岩谷峠から真弓に下る尾根は最近歩いていないので失敗するかもしれない・・・、積雪があれば山頂到着が遅れバスは1~2本遅れるだろう・・・などなど色々と考えてしまう。積雪はもう融けているだろうと思われるが、一応軽アイゼンをザックに入れ準備する。
朝の天気は晴れで散策にはいい天気である。でもこの時期の天候は寒暖差が大きいので服の調整が難しい。バスに乗ると割と空いていて座ることが出来た。でも朝の渋滞で数分の遅れ、「ギリギリの登山だな~」と哲郎。でも仁和寺を過ぎると乗客も減り・・・それでも渋滞で7分遅れで杉坂口バス停に到着。
 |
 |
| 杉坂口バス停で降り橋を渡る | 直ぐの分岐を左の林道(杉坂大谷線)へ |
今日は雨も雪も降っていないので、準備は供御飯峠の登り口でしよう!と橋を渡り林道へ向かう。すぐの林道分岐から歩きはじめると左にはフットサル用のコートが続き、右手には立派な満開の蝋梅の花を見る。
 |
 |
| 左にはフットサル用のコートが続き | 満開の蝋梅の花を見る |
 |
| 林道はしばらく清滝川に沿って |
途中で準備を先にしよう!と林道半ばで小休止する。供御飯峠への分岐に着き、早速登り始める。哲郎はここで標高を合わせていると、道子は先に急ぎ足で登っていくので急いで後を追いかける。
急勾配の林道を一登りすると林道は分岐し、供御飯峠へは右手の折り返し登っていく林道を進んで行く。ここも勾配がキツイ。少し登ると林道は折り返し西へと登っていく。林道が緩やかになり植林地の中を歩きはじめると、直ぐ右手に折り返し登っていく古道があるのでこれをとる。
 |
 |
| 橋を渡ったところが供御飯峠取付き | ゲート横の古い標識 |
 |
 |
| 細い林道を登っていく | 直ぐに折り返し登っていく道へ |
林道は古道迄だったが、最近林道は延長されたので、古道分岐を通り過ぎないように要注意。細い道を登っていくと直ぐに供御飯峠に着く。地蔵小屋の前で小休止とする。この地蔵は数年前までは峠の少し上にあったが、小屋下の崖が崩れてきたので峠に新調されている。
 |
 |
| 供御飯峠への林道 | 林道から供御飯峠への古道へ |
 |
| 供御飯峠に着く |
右手の尾根を登り始める。最初は急な植林地、溝状の道は歩きにくいので最近は植林地の中を登っていく、と言っても急斜面でシンドイ。数分登ると緩やかな雑木の尾根に変わる。ここから標高530mの尾根分岐まで北へ緩やかな雑木道が続き心地よく歩くことが出来る。と言っても綺麗な雑木が続くわけでもないが、何故か心地よい。
 |
| 峠から植林地の中を登っていく |
 |
| 緩やかな雑木の尾根に変わる |
尾根に道はないが細い尾根で歩けるところを歩いていく。途中にソヨゴの木をたくさん見るが、どの木にも赤い実は見当たらない。昔はたくさん咲いていたが年々減ってきて最近は見かけなくなった、気候変動の影響だろうか。先を歩く道子がなにやら見つめている、アセビのツボミであったが、咲くのは春先である。
 |
| 細い雑木が続く |
 |
| 雑木は段々太くなる |
尾根に太い木が増えてきてブナの木を見るようになるとP530の尾根分岐が近い。少し登り始めると尾根分岐に着き左手の尾根と合流する。ここから尾根は北東に変わり尾根は植林に変わる。
 |
| P530の尾根分岐に出合う |
数分進むと下り始め、降り立った鞍部から目の前の尾根を登っていく。右手にユックリ登っていく斜面は雑木の尾根だが密集はしていない。尾根に乗ると緩やかな雑木の尾根を進んで行く。細い雑木が増えてくるとP534のマークを見る
 |
 |
| 直ぐに鞍部へ下り | 直ぐにP534の尾根へ登り返す |
 |
| P534の尾根 |
少し進むと下り始め、遠くに木々で霞んだ半国高山のピークを見る、昔ははっきり見えた山頂も木々が伸びてきて霞んできた。下った尾根は余り登ることもなく進んで行くと、右手から植林が迫ってきて植林の端を歩くことになる。ここを歩くと、もうすぐ鞍部に下り林道に接する事が分かる。
 |
| P534過ぎの尾根 |
 |
| 少し下って次の尾根へ |
 |
| 植林に出合うと林道支線の鞍部へ下る |
尾根に植林が現れると下り始め鞍部に降り立つ。山頂までの最後の鞍部である。この鞍部で左手から登ってくる細い林道に出合い尾根下を登っていく。ここから尾根によじ登っても良いが「シンドイ!」と最近はこの林道を歩くことにする。
 |
 |
| 鞍部へ降りていくと左に林道が | 鞍部で林道支線に出合う |
林道と言っても細くて荒れた林道で急勾配で登っていくので楽ではない。今日は久し振りの山行きで短距離だがここの上りはキツイ。頑張って8分で登り林道終点の尾根に着く。山頂はもうすぐだが、あと急な植林地を標高差100m登ることになる。尾根は直ぐに荒れた急勾配に変わる。哲郎の足はもう痛くなっているが一気に登ってハーハーと息切れ、道子に遅れてしまう。
 |
| 林道が終わると最後の植林地を登る |
 |
| 荒れた急勾配の植林地に変わる |
植林地を登りったところには大きなソヨゴの大木が台風で倒れている。もう6年倒れているが細い枝が上方に伸び健在である。と言っても登山道を塞いでいるので大きく迂回することになる。倒木を過ぎると穏やかに登っていく尾根は雑木に変わり心地よく登り直ぐに山頂に着く。
 |
| 倒木を過ぎると山頂まで緩やかな雑木道 |
山頂広場は見晴らしもなくひっそりしている。11:25なので、ここでユックリ昼食としていたら予定の12:58のバスに間に合わないので、小休止して直ぐに下山開始とする。下山11:30開始、この時刻なら林道支線コースで十分予定のバスに間に合うが、バス停でユックリ着替え昼食をとる時間が欲しいので急ぎ足で下っていく。
 |
| 山頂から直ぐに下山する |
山頂から登ってきた雑木の尾根を下るとソヨゴの倒木にであう。ここは右端から左端へ倒木下をぐるりと回っていく。ここが重要でぐるりと回らず倒木の右端から下っていくと違う尾根を下ってしまう後で苦労することになる(少々危険/哲郎も1回間違いました)。
倒木下の下山ルートまで来て下り始めるが、元気のよい道子はどんどん先へと下っていく。植林地の左端を下るのだが倒木が続くので歩きにくく要注意、それでも倒木が年々減ってきていて有難い。急な植林地を下り降り一安心、山頂から17分下って林道支線の先端に着く。
 |
 |
| 山頂から雑木の尾根を下る | 荒れた植林地を下る |
ゴロゴロした道は林道というより作業道で歩きにくい、積雪があればアイゼンでスイスイ下れるのだが。尾根の鞍部まで下ると道は曲がり北西に伸びる尾根下を歩く。数分下ったところで道は折り返し斜面を巻いて下っていく。谷筋に出合った所で道は崩れ40cm位残った道をユックリ下る。崩壊ヶ所を過ぎると急ぎ足で下っていく。
 |
 |
| 植林地が緩やかになると林道支線へ | 林道が折り返すともうすぐ岩谷林道 |
前回岩谷林道手前でたくさん倒木があり、苦労して岩谷林道に降り立ったが、周辺は整備され新しい苗が植えてあった。12:03岩谷林道に出合う。後は林道ゲートまで30分、岩戸落葉神社で後始末、着替えて昼食・・と、十分バスには間に合いそうである。
ところが道子は岩谷林道をピッチをあげ下り始める、着替えや昼食をユックリしたいからだろう。哲郎も後を追うように下っていく。積雪はなく春の花もなく、植林地が続く谷沿いの林道は歩くだけ・・・。
 |
 |
| 岩谷林道に出合う | 岩谷林道は急ぎ足で下る |
岩谷林道入口のゲートが見えてくる。12:20である。予定で30分の林道歩きを、道子の頑張りで20分で下ってきた。ゲートを抜け岩戸落葉神社に寄り靴や用具を洗う。哲郎は神社の舞台で着替え、道子は派出所へ向かいトイレを借り着替える。
 |
 |
| 岩谷林道のゲートに着く | 岩戸落葉神社に寄り |
着替えの終わった哲郎も派出所へ向かい昼食とする。今日はパトカーがいないので、ただいま巡回中だろう。その横で二人はオニギリを食べ始める。今日は陽射しが暖かく心地よい、でも目の前の周山街道は猛スピードの車が通り抜けるので静けさはない。
そろそろバスがやってくるだろうとバス停へ向かう。近所の男性がバスを待っていて、今年は5cmの積雪が2回あったとのこと。彼は昔は山が好きでアルプスはほとんど登ったと言っていた。話をしていると定刻にバスがやってきて、二人は帰路に着く。
半国高山は単純な低い山だが、二人は今年も十分楽しめたようである。



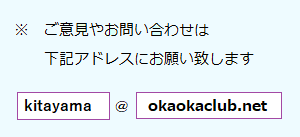

|

|