 京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
 京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub
京都北山を中心とした山々を楽しむ okaokaclub

芹生峠への緑の尾根を楽しむ




|

|
日程:
・2025.11.17 (水) 晴れ 哲郎・道子

|
行き: 烏丸北大路バス停 7:33(出町柳 7:20) - 花背峠(京都バス) |

|
帰り: 貴船バス停 14:06 - 貴船口バス停 14:39 - 国際会館(京都バス) |
コース:
・花背峠~天狗杉~旧花背峠(地蔵小屋)~芹生への林道~芹生峠への尾根~鉄塔~芹生峠~アソガ谷林道出合~奥貴船橋~貴船バス停~貴船口バス停~国際会館バス停
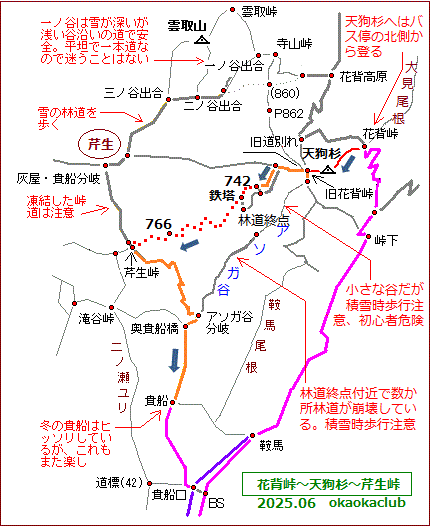



旧花背峠先の林道分岐点から芹生峠への尾根、以前梅雨時に歩いた時、尾根下の谷間が真っ白く染まっていて感動したことがある。今日はその風景を楽しもうと出かけるが、さてどうだったのだろうか?
今日はエゴノキの花が半分残っていてウツギもシッカリ咲いていたがヤブデマリが全く見えない、ちょっと早かったのか?と谷間に下って確認しようと思ったが草茂る谷間は「ヒルがね~」と諦める。
もう一つの目的は芹生峠付近の道に咲くミヤマタゴボウとオオハンゲの花鑑賞であるが、こちらも花が極端に減り残念ということになる。



烏丸北大路7:33発広河原行きのバスは早朝にも関わらず通勤の客で一杯、バス停に早くから並んでいたので座ることが出来た。朝早いので京都産業大学の関係者ではなく市原周辺の通勤客である。市原バス停を過ぎると乗客は減り、いつもの静かな広河原行きのバスとなる。
花背峠バス停で降りる。気温は24℃とある心地よい。バス停で準備するが、足元にエゴノキの花を見るが木にも半分花が残っている。、ガマズミの花は終わりかけている状態なので、前回来た時よりもちょっと早く来たような気がする。否、異常気象で花によっては遅れているのかも知れない。。
 |
 |
| 花背峠に着く | 散ったエゴノキの花が一杯 |
積雪時は登りで苦労する斜面の道はスイスイと登れ、直ぐに支尾根に乘る。少し登ると倒木帯の広場に着く。今日は右から左にくるりと回って迂回し支尾根に戻る。山々に白い花が少なく、もう咲き終えた花もあるが、これからの花が多いようである。しばらく左手の雑木の緑を見ながら登っていく。
 |
 |
| バス停傍の登山道から登る | 雪でしんどかった道もスイスイと |
 |
 |
| 尾根の右手は植林、左は緑の雑木 | 山々に白い花が少なく |
木によって開花条件が異なるので、何が咲き終えた花、何がこれから咲く花かは、よく観察しないと分からない。それは面倒だと二人はスイスイと登っていき天狗杉山頂へ向かう。木の根道を登りきり、緩やかになり雑木の間を1分も進めば天狗杉山頂に着く。花背峠登山口から30分である。
 |
 |
| 木の根道を登って行くと | 山頂広場の雑木の中を進む |
 |
| 天狗杉の三角点に着く |
このピークは雑木の中にあるので展望はない。直ぐに旧花背峠へと下っていく。山頂の南側に下っていく道を見るので、後はこの道を辿り下っていく。南へ下っていく道は直ぐに西へ向いてきて、地形図にある支尾根を下っていく。
 |
| 天狗杉の西尾根は心地よい雑木が続く |
途中で尾根が広くなって来るので道がハッキリしない場合は、尾根の右端を歩くと良い。この道も緑の雑木が続き心地よく歩くことが出来る。途中で左手にフェンスを見てそれに沿って下っていく、チマキザサ保護区のフェンスである。
フェンスが切れると周囲は植林に変わる。道なりに下っていくと旧花背峠の地蔵が見えてきて、林道に降り立つ、天狗杉山頂から15分である。まだ9:30、飲水休憩後直ぐに西へ芹生へと下る林道を歩きはじめる。
 |
 |
| 途中からフェンスに沿って歩く | フェンスが切れると周囲は植林に変わる |
 |
| 林道に降り立つと 目の前に旧花背峠の地蔵を見る |
林道途中で南に京都市街地を見ることが出来るが、今日はスッキリしない天気でハッキリ見えない。旧花背峠から10分歩くと芹生峠へ続く尾根分岐に着く。いつもは尾根下の林道を詰めていき、・742付近で林道から右手の尾根の鞍部に登っていたが、「今日は林道の陽射しが強いかも」と、最初から尾根に乘ることにする。さっそく尾根の先端から登り始める。
最初は急斜面を登ることになる。直ぐに登り終えると密集した雑木が続くが、直ぐに心地よい雑木の尾根に変わる。後は適当に尾根の高い所、歩き良い所を進んで行けば良い。尾根の低い所を歩いていると尾根から下ってしまうこともあるので、高い所の歩き良い所を進んで行く。
 |
 |
| 林道分岐から尾根の端から登っていく | 急斜面を登ると雑木を掻き分けて |
 |
| 可能な限り尾根の高い所を歩く |
そのうち尾根は下り始め・742の林道鞍部に降り立つ。ここから関電巡視路の階段を登って行き鉄塔広場を目指す。標高差30mぐらい登って鉄塔広場に着く。階段があるので苦にならない。
ここからは尾根のピークを辿って芹生峠へ向かう。この鉄塔広場から次のピークへの下降点は南にあるので鉄塔をぐるりと左へ回って下降点へ向かう。鉄塔から西へ、送電線に沿った支尾根は目的の尾根では無いので、ここは要注意!
 |
 |
| 関電巡視路の階段を登る | 鉄塔をぐるりと左へ巻いていく |
 |
 |
| 送電線に沿った西の支尾根はルート外 | 下降ポイントから鞍部へ下る |
鉄塔の南へ回ってくると雑木の合間から下ることが出来るポイントが数カ所ある。昔付けたマークは分からなかったが、後からやって来た登山者のマークがたくさんあり、どれを下っても同じ鞍部に降り立つことが出来る。
次の鞍部は標高差20m下付近にあるので、少し下って斜面の下に鞍部が見えなければ登り返したほうが良い。鞍部とはピークとピークの間の谷間なので、次のピークへ登って行かなければ鞍部ではない。
鞍部に降り、西の谷に広がる木々を見る。目的の白い花鑑賞である。少し白っぽくなっているが感動するような光景ではなく、今回は残念!ということになる。谷間を下り何の木が咲いているのか、散っているのか調べに言っても良かったが、斜面は深い草が続くので「ヒルが心配!」と諦める。
 |
| 谷間の白い花はこれからだった 手前の白はウツギの花 |
鞍部に咲いているエゴノキの花、ここの花を見ると半分ツボミだったので、「あ~少し早かった!残念!」と。ただウツギだけは綺麗に咲いている。次のピークへ登っていく。次のピークは小さなピークで何も咲いていないので、次の鞍部へと下っていく。
 |
 |
| ここのエゴノキはツボミがあり 咲き始めだった |
どのピークも花は少ない |
鉄塔から芹生峠まで鞍部が8カ所あるので高低差が少ないと言えどしんどい所だが、花鑑賞しながらユックリ進んでいるので疲れはない。
 |
| 時々楽しませてくれる鞍部の花 |
そのうち鞍部に草が無くなってきて花も少なくなる。コース半ばを過ぎると花は少なくなったので、ただ黙々と歩いていて集中力も薄くなり何処を歩いているか確認もしなくなる。
ピークへ登っていくと大きな倒木があり、ここは大木をぐるりと巻いて尾根を右へと進んで行く。尾根を左へ下ると芹生峠下の地蔵小屋下っていくようだが、まだ確認はしていない。ここから左手の植林の横を歩いていく。このコースで植林に接するのは初めてで、芹生峠への下降点まで後20分くらいである。
 |
 |
| ピークの大きな倒木はぐるりと巻いて | 植林に接すると下降ポイントまで20分 |
後は迷うような所はなく、ただ黙々と歩いていく。「あ!ここだった!」と芹生峠北の林道へ下るポイントに着く。ここは植林横の細い雑木の支尾根があるので分かる。そこを下っていくとこの支尾根で倒木を見る。「新しい倒木?」、よく見るとここはビンが数本放置してあった所だった。何時ものように「このビンは何なの?お酒?薬品?」と思ってしまう。
 |
 |
| 植林地に沿った細い支尾根を下る | 「このビンは何なの?お酒?薬品?」 |
最後は植林の急斜面を下って芹生峠北の舗装道へ降り立つ。「なんだ?」と北の方から重機の音がするので確認に行くと、舗装道西側の斜面の木の伐採が済、植林の為だろう重機で地面を耕していた。
11:30過ぎ、昼食とするが芹生峠ではヒルがいるかも知れないと少し下った地蔵小屋へ向かう。地蔵小屋に着き横の細い流れで用具を洗う。「ヒルや~!」と道子、ヒルは何処にでもいるようだ。ゆっくりの昼食も終わり貴船へと下っていく。
今日の目的の一つはミヤマタゴボウとオオハンゲと・・・の観察、数年前には道端にたくさん咲いていたのだが、探さないと見つからない状態、ミヤマタゴボウは5株しか見つからなかった!。
貴船まで来ると休日のような人出、この暑い中歩いている人や店に並んでいる人は皆海外の観光客であった。「暑いのにご苦労様です!」。貴船~貴船口間のバスは行きも帰りも長い列が出来ていて処理出来ていないような気がする。そんなに貴船っていい所なのだろうか?



 |
 |
| キランソウ | ミヤマタゴボウ |
 |
 |
| オオハンゲ | サワギク |
 |
 |
| ヤマアジサイ | ヤマゴボウ |



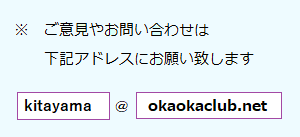

|

|